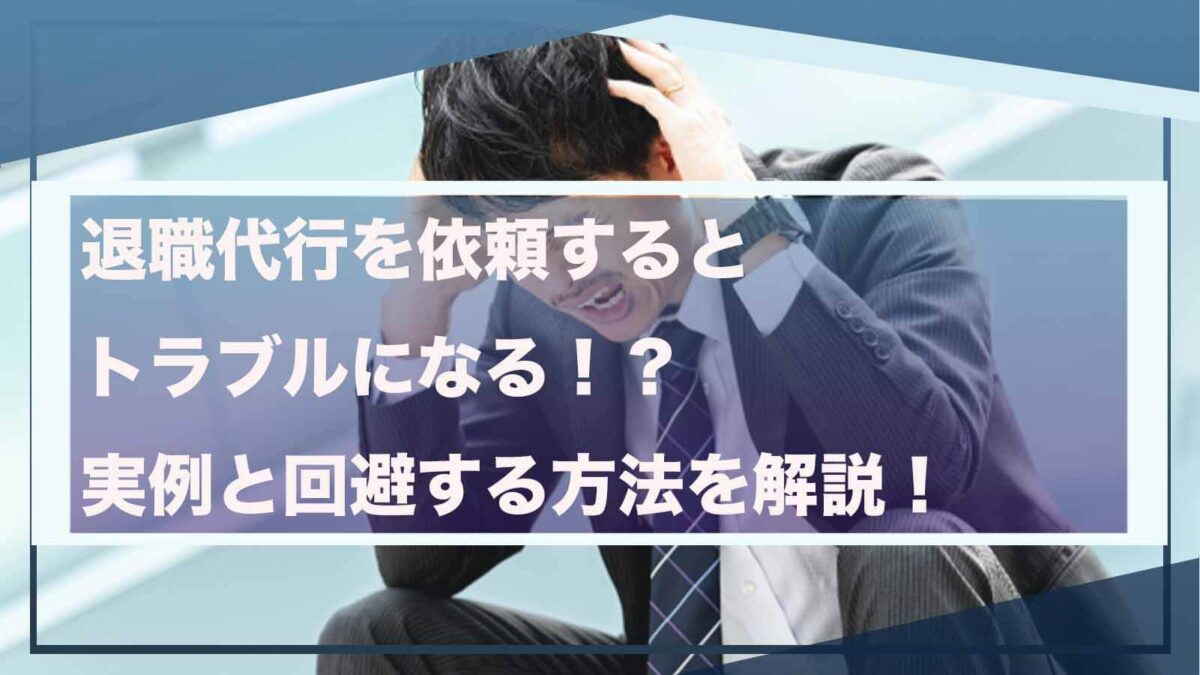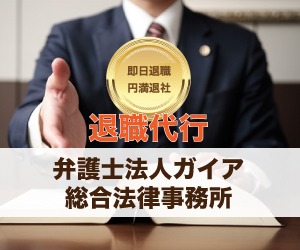- 退職代行の利用で起きうるトラブル
- トラブルを回避する方法
- 利用後のフォローアップと対応策
退職は人生の大きな節目のひとつ。
最近では、退職代行サービスを利用してスムーズに退職を進める方が増えています。
ただ初めての利用することを考えている方は、「本当に大丈夫?」「トラブルが起きないか?」といった不安を感じるのも無理はありません。
参入する企業の増加とともに”退職代行をめぐって会社or代行業者とのトラブル”も発生しています。
この記事では、退職代行利用時に起こり得るトラブルとその対策、安心してサービスを使うためのポイントを詳しく解説していきます。
退職代行サービスの基本的な情報

退職代行サービスは、依頼者に代わって勤務先へ退職の意思を伝え、手続きを進めてくれるサービスです。
会社や上司と直接やり取りする必要がないため、ストレスを大幅に軽減できます。
依頼から退職完了までのフローは業者によって異なりますが、基本的には連絡手段を明確にし、必要書類の準備などのサポートをしてくれます。
利用する人の多くは20〜40代の働き盛りの世代です。
働き方改革や精神的負担を避けたいという意識の高まりとともに、退職代行の利用件数も年々増加しています。
また、ブラック企業の存在やハラスメント問題が社会的に注目される中で、自衛手段としてサービスを活用する人も増えています。
 SUSUMU
SUSUMU信頼できる業者がある一方で、参入が容易な業界でもあるため、選定には注意が必要です!
退職代行のサービス選定時に重視すべきポイント


サービスを選ぶ際には、料金の安さだけで判断するのではなく、実績やサポート体制、利用者の評判なども確認しましょう。
公式サイトに掲載されている実績数や第三者の口コミ、対応のスピードや丁寧さは、信頼性を見極めるための重要な判断材料です。
退職代行は、面倒な会社とのやり取りから解放されるのが最大のメリットでしょう。
特に精神的な負担が大きいケースでは、第三者が介入することで冷静に安全に退職を進められるという安心感があります。
ただその一方で、「業者の対応が不十分だった」「会社側が連絡に応じない」場合などは、想定外のトラブルも考えられます。



契約内容を事前にしっかり確認し、疑問点を残さないことが重要です!
退職代行の利用で起きるトラブル【代行業者編】


トラブルを防ぐためには、「事前にどのような問題が発生しえるのか?」を把握することが大切です。
退職代行を通じたやり取りでは、依頼者と業者、業者と会社の間で意思疎通がうまくいかないケースがあります。
メールや書面での明確なやり取りを徹底し、口頭のみのやり取りは避けるべきです!
- 違法行為を行うサービスを利用した
- 料金体系と追加費用の不透明さ
- 悪徳業者に依頼してしまった
- サービスが十分ではなかった
- 法律問題に対応できない
- 個人情報の管理とプライバシー保護の問題
違法行為を行うサービスを利用してしまった
民間・労働組合・弁護士が参入する退職代行サービス。
しかし業態によっては対応できない業務があり、それを業者が行ってしまうと違法行為になり、依頼者であるご自身にも影響が及ぶ可能性があります。
「労働者の退職の意思を会社に伝える」
これだけならどの業態が行っても合法とされています。未払い給与の請求や退職日の調整、有給休暇の取得の調整などの交渉は「非弁行為」にあたり、弁護士以外が行うと違法になってしまいます。
労働組合は例外として”団体交渉権”を使用すれば可能ですが、民間業者はそうはいきません。
違法行為を行っている業者を利用してもご自身が逮捕されることはないでしょうが、『退職が無効になる』『警察や検察から聴取を受ける』ことは予想できます。



事前に会社との交渉が必要そうなら、弁護士・労働組合が運営するサービスに依頼しましょう!
料金体系と追加費用の不透明さ
退職代行の料金は一見シンプルに見えても、ケースによっては追加費用が発生することがあります。
例えば、地方への対応や即日対応、有給交渉の有無によって料金が変動するなど場合です。
契約書に明記されているか、見積もりに全て含まれているかを確認することで、予期せぬ請求を避けられます。
悪徳業者に依頼してしまった
一般的に民間なら約2〜3万円、労働組合なら約3万円、弁護士なら約5~10万円とされる利用料金。
一部では「コミコミで1万円!」「先着〇〇様まで半額!」といった宣伝文句を使う業者も存在します。
万が一こうした業者に代行依頼をしてしまうと、次のような被害にあう可能性もあります。
- 申し込み後、業者と連絡が取れなくなった
- 最初聞いた料金の何倍もの料金を請求された
- 料金は払ったけど、対応してくれなかった



極端に料金が安い業者はさけ、知名度や実績を持った業者を選ぶのがオススメです!
サービスが十分ではなかった
業者に退職の意思は伝えてもらえても、ご自分が依頼していたサービスが受けられないこともあります。
パンフレットや公式サイトに記載された内容と実際の対応に違いがあれば、利用者は強い不信感を抱くことになります。
- 即日対応のはずが退職日が何日も伸ばされた
- 有給の取得ができなかった
- 未払い給与の対応がされなかった
- 必要書類の請求がされていなかった など
他にも「追加料金が発生する業務が事前に説明されていない」「会社側との交渉を代行できないと後から判明する」などのケースです。
こういったことは悪徳業者ではなくても起こることはあります。
たとえば、先ほど言ったような「民間では交渉が行えない」、未払い賃金の関係では「請求できるほどの証拠が集めれなかった」場合など。



契約前に細かい条件を確認し、説明が不十分な場合はその業者の利用を再考すべきです!
法律問題に対応できない
損害賠償請求などの法律問題には弁護士しか対応できません。
就業中の怪我、職場内でのいじめやパワハラなどのハラスメントでのうつ病やPTSD。
こういった労働問題から退職を希望する方は多いです。
しかし、その原因が仕事にあって訴えたい場合でも、民間や労働組合の代行サービスでは対応できません。
「退職したことで顧客との契約が解除される」「会社の業務が止まった」など、会社に大きな損害を与えてしまえば損害賠償請求や懲戒解雇となることはありえます。



退職代行を使って安心・安全に辞めたい方は弁護士の退職代行がオススメです!
個人情報の管理とプライバシー保護の問題
退職代行の利用には、個人情報の提供が不可欠です。
氏名や勤務先、連絡先など、非常にセンシティブな情報を扱うため、業者のセキュリティ体制が万全かどうかも重要なポイントです。
プライバシーポリシーが整備されているか、第三者への情報提供がないかなども確認しておくと安心です。
\27,500円から弁護士に依頼できる!/
退職代行の利用で起きるトラブル【会社編】


- 退職できなかった
- 脅される
- 必要書類を送ってくれない
退職できなかった
せっかく退職代行を依頼しても、会社を辞められなかったケースも存在します。
- 退職の連絡を無視され、辞められなかった
- 出社を促され、会社からの引き止めにあってしまった
- 民間業者が会社との交渉を行ってしまい、退職を拒否された
退職代行サービスに対する世間の知名度が上がることで、会社側も知識や対策を身につけていることも予想できます。
”民間なら交渉はできない”ということを知っていて代行業者からの連絡を無視したり、「退職には出社が必要」と連絡し、引き止めを行うケースもあります。
そうならないためにも、退職代行を依頼する場合には労働組合もしくは弁護士が運営するサービスが安心です。
脅される
即日退職や引き継ぎなしでの退職する場合、会社から「損害賠償請求をする!」「クビにする!」と脅されることもあります。
しかし、従業員が1人辞めるくらいでは実行されることはないでしょう。



引き継ぎなしの場合、大きな損害が生まれると損害賠償請求や懲戒解雇される可能性はゼロではありません!
必要書類を送ってくれない
退職には成功しても、離職票や源泉徴収票といった書類を会社側が送ってこないトラブルもあります。
こうした書類は失業保険を受けるためや確定申告、転職時に必要になる重要な書類です。
退職後にこうならないためには、きちんと代行業者に相談し、事前に会社へ伝えてもらうと良いでしょう。



退職代行の中には退職後のサポートを積極的に行ってくれる会社もあるので、事前にチェック!
退職代行でのトラブルを回避する方法10選


退職代行サービスは「出社せずに退職ができる」という便利で頼りになる一方で、予想外のトラブルに巻き込まれることもあります。
そういったトラブルを限りなく減らすためには次のような点に注意しておくと良いでしょう。
信頼できる業者を見極める目と契約内容の理解などがトラブルの予防につながります。
- 1番安心できるのは弁護士
- どの業務まで対応できるか?
- 即日退職の可否を確認
- 法的リスクの確認
- 業者としっかりコミュニケーションを取る
- 業者選定に向けた情報収集の方法
- 契約書および利用規約の徹底チェック
- サポート体制と問い合わせ窓口の確認
- 事前に返却物は準備しておく
- 引き継ぎ資料なども準備
1番安心できるのは弁護士の退職代行
退職代行を依頼する場合に1番オススメできるのは弁護士の退職代行サービスです。
- 退職の意思を本人に代わって会社に伝える
- 有給取得など、会社との交渉ができる
- 損賠賠償請求などの法律問題も対応可能



”これら全てに対処ができるのは法律のプロの弁護士のみ”です!
どの業務まで対応できるか?
理想的なのは弁護士への依頼ですが、その場合次のようなデメリットもあります。
- 費用が5〜10万円と高い
- 24時間対応、LINE対応の事務所も少ない
- 未払い給与や退職金の請求などの金銭回収の場合、別途成功報酬が必要
特に体や心の限界から「今すぐに会社を辞めたい」という方。
「法律問題に対応してもらう必要がない」という方の場合には、労働組合が運営する代行サービスの方が合っているケースもあります。
ですので次のように業務によって依頼する業者を選ぶのも良いでしょう。
『退職の連絡だけを対応してもらいたい』→【民間】
『退職の連絡+会社との交渉を対応してもらいたい』→【労働組合】
『退職の連絡+会社との交渉+法律問題も対応してもらいたい』→【弁護士】
即日退職の可否を確認
即日退職を希望する場合、すべての業者がこれを対応できるわけではありません。
「即日退職が可能かどうか?」は事前に確認しておくことが大事です。
また、即日退職には会社側の協力が必要な場合もあるため、現実的に可能かどうかのアドバイスを受けることも重要です。
法的リスクの確認
退職代行サービスが提供できる範囲は法的に制限されています。
例えば、一般の業者では法的な交渉や未払い賃金の請求を行うことができません。
これらを行うためには、弁護士に依頼する必要があります。



法的に問題ないサービスかどうか事前に確認しましょう!
業者としっかりコミュニケーションを取る
退職代行サービスを依頼する際に、自分の状況や希望を明確に伝えることが重要です。
会社とのトラブルの内容や希望する退職日、退職後の処理など、細かく業者に伝えることで、円滑に手続きが進む可能性が高まります。
適切なコミュニケーションを取らないと、サービスの提供がスムーズに進まないことがあります。
業者選定に向けた情報収集の方法
一つの業者に絞る前に、複数の情報源から比較検討することが基本です。
公式サイトの情報だけでなく、第三者のレビューやSNSの声も参考になります。
特に口コミでは、実際に利用した人の体験談が掲載されていることも多く、実態がつかみやすくなります。



あまりにも良い評価ばかりの場合は、やらせの可能性もあるため注意が必要です!
契約書および利用規約の徹底チェック
契約書に目を通すことなく依頼してしまうと、後から不利な条件に気づくことになりかねません。
料金の内訳やキャンセル時の対応などは特に注目しておくべき項目です。
退職代行の料金は一律に見えても、オプションや対応範囲によって大きく異なります。
また、依頼後のキャンセルに関する規定も業者によって違いがあるため、トラブル回避のためには必ず確認しておきましょう。



内容に疑問がある場合は、依頼前に質問して明確な答えを得ておくことが重要です!
サポート体制と問い合わせ窓口の確認
万が一、トラブルが起きた場合に、迅速に対応してもらえるかどうかは安心材料として大きなポイントです。
24時間対応の有無やメールだけでなく、電話やチャットなど複数の窓口があるかどうかを事前に確認しておきましょう。
対応の丁寧さやスピードも、業者を見極める指標のひとつです。



最近は多くの代行業者でLINEやメールでの連絡が可能になっています!
事前に返却物は準備しておく
会社から借りている制服やパソコン、社員証などは退職後に返却するのが一般的です。
中にはこういった返却物を直接会社に持ってくるように連絡してくる会社もあります。
代行業者を通じて郵送で返却することを伝えてもらい、後日ご自身で会社へと郵送できるように対処してもらいましょう。
またご自身が社内で使っていたロッカーやデスクに私物が大量にある場合。
「なるべくなら退職代行へ依頼する前に整理や持ち帰っておく」のがオススメです。



難しいようなら「親しい同僚に送ってもらう」「業者を通じて自宅へ郵送(着払いで)してもう」ように相談!
引き継ぎ資料なども準備
退職代行で会社を辞めるケースでは引き継ぎが十分にできず、会社とトラブルになることも多いです。
それを防ぐために「ご自身の業務内容や取引先の情報、ノウハウなどをまとめた資料やファイルを制作しておく」と良いでしょう。
急な退職で事前に作成できなかった場合は、後日郵送するといった方法でも構いません。
\22,000円で依頼できる!/
利用後のフォローアップとトラブル対応策


退職代行は、”依頼すれば終わり”というわけではありません。
「退職後に書類が届かない」「会社からの問い合わせがくる」などと、予期せぬ対応が必要になることもあります。
最後まで安心して退職するためには、サービス終了後のフォロー体制や自身でできる確認作業も重要です。
ここでは、利用後に行うべきフォローアップと万が一のトラブル時に備えた対応策について解説します。
退職完了後の確認事項
退職代行を通じて退職手続きが完了したとされても、自身でも確認すべき項目もあります。
「退職届が正式に受理されているかどうか?」「社会保険の手続きが完了しているか?」「離職票や源泉徴収票などの必要書類が確実に届いているか?」などはチェックすることが大切です。
これらの確認を怠ると、後に失業保険の申請や転職先に書類を出す際などに支障をきたすことがあります。



代行業者からの報告を待つだけでなく、自身でも確認する姿勢を持ちましょう!
トラブル発生時の初期対応
万が一、会社側からの書類が届かない、離職日が間違っているなどのトラブルが発生した場合は、まずは代行業者に連絡し、対応を聞きましょう。
その際には、やりとりの記録を残しておくのがポイントです。
また、対応に不備があると感じた場合は、消費生活センターや労基署などの公的機関に相談するのも一つの手です。
焦らず、冷静に事実を整理しながら対応することが、スムーズな問題解決に繋がります。
退職後のサポート内容の確認
信頼できる代行業者は、サービス完了後も一定期間のアフターサポートを提供している場合があります。
書類の追送や会社との追加連絡が必要になった場合の対応などが含まれることが多いです。
事前にサポート内容を確認し、必要に応じて利用することで、より安心して退職することができます。
自分自身の対応力も重要
退職代行を利用したとはいえ、すべてを任せきりにするのではなく、自分自身でも退職の流れや必要書類、会社側の対応をしっかりと把握することも大切です。
業者側に依存しすぎず、自ら確認・行動することで、トラブルのリスクを大きく減らすことも可能になります。



退職は今後の人生にも関わる大きな出来事のため、最後まで責任を持ち対応しましょう!
退職代行利用時のトラブルについて:まとめ
この記事では、退職代行利用時に起こり得るトラブルとその対策、安心してサービスを使うためのポイントを詳しく解説してきました。
退職代行サービスを利用しても、ほとんどの場合では何のトラブルもなく無事に退職できます。
ただ、伝える会社側がブラック企業であったり、代行サービスの増加で違法業者が出現するなど、トラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。
事前の準備と情報収集、契約内容の確認、そして利用後のフォローアップまでを丁寧に行うことで、多くのトラブルは回避することにつながります。
初めて利用する方にとって退職を代行してもらうことは不安も多いかもしれません。
ですが、この記事でご紹介したポイントを押さえておけば、安心してサービスを活用でき、退職という大きな一歩を後悔のない形で踏み出せるでしょう!