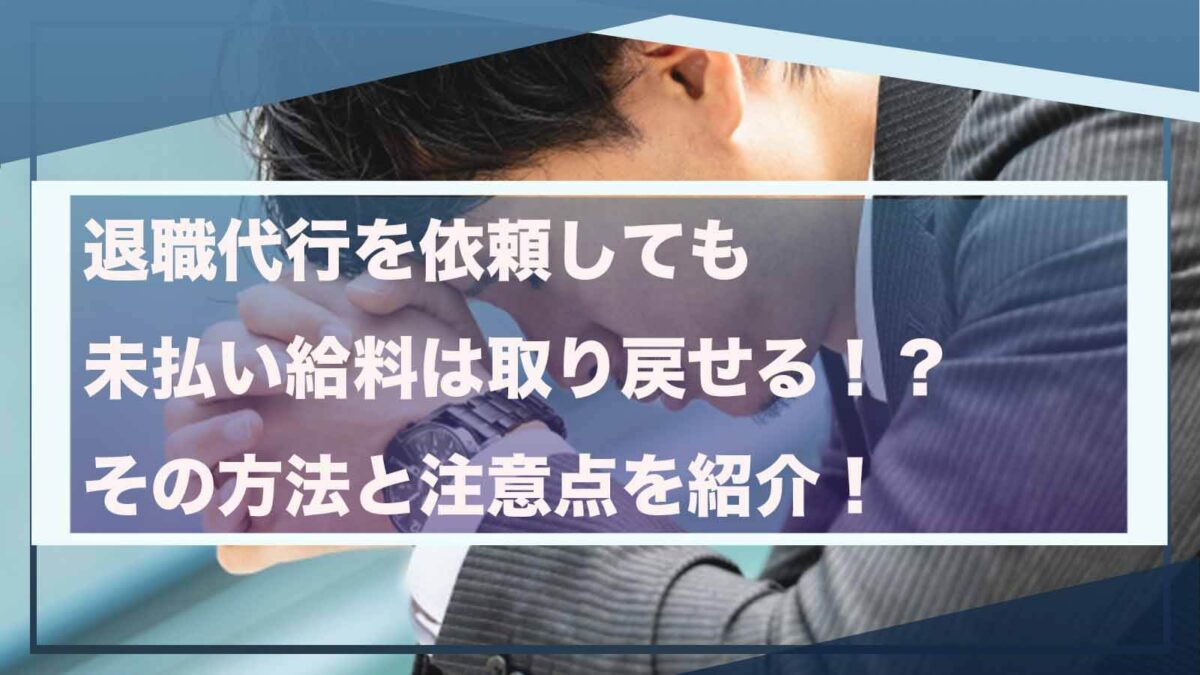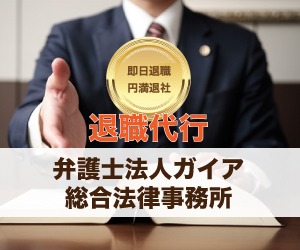- 未払い給料や残業代の定義
- 利用して未払い給料を取り戻す際の注意点
- 退職代行で未払い給料を取り戻す方法
退職代行サービスを利用する方には様々な理由があります。
中でもパワハラやセクハラに次いで多いのが、給与や残業代などの未払い給料に関する理由です。
こうした給料の未払いは、在職時には「言いづらい」「伝えたけど対応してもらえない」といった部分があり、会社との溝を生みやすい問題です。
また、退職時に自分で対応しようとしても「やり方がわからない」という方も少なくありません。
しかし退職代行サービスを利用する場合、こういった未払い給料にも対応してもらえるケースも多いです。
そこで本日の記事では、退職代行サービスを利用した場合に未払い給料を取り戻す方法や注意点などについて解説していきます。
\安心安全の弁護士に依頼する!/
未払い給料・残業代とは?
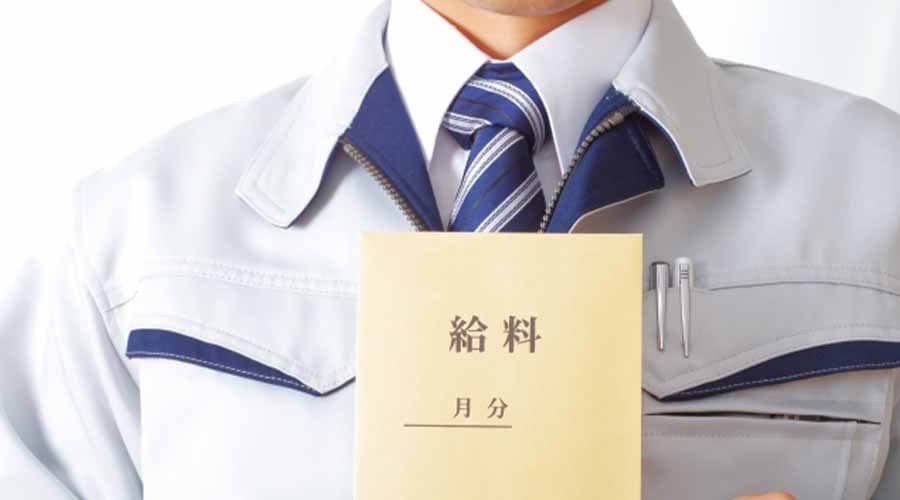
退職代行を利用する際、最も多い懸念のひとつが未払い給料の存在です。
未払い給料の対象になるのは次のようなものです。
- 一般的な給与(月給や日給など)
- 退職金
- 一時金(ボーナスや賞与など)
- 割増賃金(残業代や休日労働、深夜業代など)
- 有給休暇の賃金
給与は労働者の正当な権利であり、たとえ退職の意思を伝えた後でも全額支払われるべきものです。
ここでは、「未払い給料がなぜ発生するのか?」また「退職代行サービスがどこまで対応できるのか?」を整理していきます。
未払い給料が発生する背景
企業側の経営難や人員不足、あるいは労務管理の不備などが主な要因となって未払い給料は発生します。
悪質な場合は会社側が意図的に支払いを遅らせたり、退職する従業員への支払いを拒むケースもあります。
もちろん法令に反することは明らかですが、「辞める際に揉めたくない、、、」などの原因から、従業員側が泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。
未払い給料に対する法的保護
労働基準法では、「労働者が退職した際には賃金を即時に支払わなければならない」と定められています。
未払いがある場合は労基署への申告や弁護士による請求など、法的な救済手段が用意されています。
これにより、未払い給料は回収可能なケースが多くあります。
 SUSUMU
SUSUMU労働基準法に違反すれば、会社側は30万円以下の罰金が科される可能性があります!
退職代行サービスの対応可能範囲
弁護士が関与していない退職代行業者では、未払い給料の直接的な交渉は行えません。
あくまで退職の意思を伝えることに限定されるため、法的交渉が必要な場合は、弁護士が運営する代行業者を選ぶ必要があります。
民間業者を依頼する場合は、利用者自身が別で労基署や弁護士に相談することも想定して準備をしておきましょう。



労働組合の運営する退職代行でも対応できます!
サービス利用時に注意すべきポイント
代行業者によっては、未払い給料の交渉に関して誤解を与える説明をする場合があります。
そのため、契約前に「何ができて何ができないか」を必ず確認し、業者選びには慎重になることが大切です。
また、退職前の給与明細や雇用契約書などは手元に保管しておくと、後の対応がスムーズになります。
労働者としての自衛策
退職前から、働いた時間や給与額などをしっかり記録しておくことも自衛につながります。
「給与明細を毎月保存する」「タイムカードの写しを取っておく」など、”証拠保全”と考えた方が良いです。
未払い給料があったとしても、証明できなければ取り戻せません。
退職時に未払いが発生した場合の相談先や対処方法をあらかじめ調べておくことも、安心して退職を進めるための備えになります。
退職代行を利用して未払い給料を取り戻す際の5つの注意点


未払い給料は本来ならもらえるご自身の給与で、会社側が支払わないのは労働基準法に違反する行為です。
ですので、退職代行を利用して会社を辞めた場合でも未払い給料は取り戻すことができます。
ただ、実際に取り戻すためには次のような注意点があります。
- 弁護士か労働組合しか対応できない
- 証明できないと請求できないケースもある
- 請求できる期間が決まっている
- 退職時の交渉に備える
- 和解金の有無を確認する
弁護士か労働組合しか対応できない
未払い給料の請求するためには会社と交渉を行う必要があります。
そのため民間では非弁行為(違法行為)になるので、弁護士か労働組合が運営する退職代行サービスに依頼するしかありません。
証明できないと請求できないケースもある
未払い給料を請求するためにはご自身が労働していた証拠を示すことが重要です。
実際に退職代行へ依頼する前に次のような書類や証拠を集めておくと良いでしょう。
- 給与明細や通帳の明細
- タイムカードや勤怠記録のデータなど実際に働いていたことがわかる書類
- 就業規則や労働契約書など労働条件が記載された書類
- 日報や残業記録など、残業時の勤務内容が書かれた書類



証拠が提出できないと、自力はもちろん弁護士でも対応できない可能性があります!
請求できる期間が決まっている(2年間を過ぎてしまうと時効)
未払い給料の請求には時効があり、請求できる期間が定められています。
その期間は2年間(2020年4月以降の発生分は3年間)となっています。
ですので退職代行の利用を考えている方で、未払いの状態が何年も続いている場合にはなるべく早い依頼が必要になってきます。
退職時の交渉に備える
退職代行サービスを利用した場合、企業側が未払い給料に対して対応を拒否するケースも考えられます。
この場合、弁護士を通じて正式に労働基準監督署へ申し立てを行ったり、裁判に進展する可能性もあります。



事前に代行業者に交渉の流れを確認しておくと安心です!
和解金の有無を確認する
退職代行を通じて未払い給料を請求する場合、企業側が和解金を提示してくることもあります。
この際、「和解金を受け取るか?」「正式な未払い給料を請求するか?」は慎重に判断する必要があります。
和解金は本来の未払い給料よりも低い場合が多いため、弁護士と相談しつつ進めることがオススメです。
\27,500円から弁護士に依頼できる!/
退職代行で未払い給料を取り戻す方法


未払い給料がある状態で退職代行を利用する際に不安になるのが、「しっかりと支払われるかどうか?」でしょう。
特に、すでに退職の意向を示している場合、会社との関係が悪化しやすく、支払いの遅延や拒否といったリスクも高まります。
ここでは、未払い給料の回収に関する基本的な知識と、実際の対応方法について詳しく解説します。
- 1番オススメできるのは弁護士
- 労働組合でも対処可能
- 労働基準監督署に申告する
- 金銭請求手続きの基本
- 交渉の進め方と注意点
1番オススメできるのは弁護士への依頼
未払い給料を取り戻したい場合、1番安心できるのが弁護士が運営する退職代行サービスを利用することです。
まず民間や労働組合が相手とは違い、弁護士の場合だと会社側の対応も違い、請求を行っただけで素直に支払うケースも多いです。
もしそれでも未払い給料の対応をしてこない場合は、次のような対応を行っていくことになります。
- 証明書類や証拠をもとに交渉を行う
- 内容証明郵便で請求する
- 最終的に民事調停・支払い催促の申し立て
こういった対応も弁護士なら安心して任せられます。



勤務先によって計算方法は異なるので、請求を行いたい場合には合わせて弁護士に相談すると良い!
労働組合でも対処可能
未払い給料の請求は団体交渉権を使えば労働組合でも対応できます。
注意点としては、「労働組合は会社と交渉はできても法律問題を解決することはできない」点です。
可能性としては低いですが、証明書類や証拠をもとに交渉を行っても会社側が支払わない場合、会社を訴えるなどの行為は労働組合には行えません。
労働基準監督署に申告する
「民間の退職代行を利用した」「労働組合に依頼しても戻ってこなかった」という方は、勤務した証拠や証明を持って労働基準監督署に申告する方法もあります。
労基署は、厚生労働省の運営組織で全国どこにでも窓口があり、誰でも無料で相談できます。
会社側に給料支払いの義務がある場合、労基署が調査や指導を行ってくれます。相談には、勤務記録や給与明細、就業規則の写しなどがあるとスムーズです。
あらかじめ情報を整理してから訪問すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。



未払い給料の支払いに応じない場合は弁護士への依頼が必要になります!
金銭請求手続きの基本
未払い給料の法的請求手段としては、簡易裁判所での支払督促や少額訴訟があります。
これらの手続きには、具体的な証拠が不可欠です。勤務時間の記録や給与明細、雇用契約書などは必ず保管しておきましょう。
タイムカードや勤怠アプリのスクリーンショット、メールでのやり取りなども証拠になります。



未払い給料の請求には時効があるので(原則として2年)、早めの行動が求められます!
交渉の進め方と注意点
退職代行を利用する場合は、自分から会社側に未払い給料の請求・交渉をすることはないでしょう。
ただ、もし自分で請求・交渉を行う場合は、冷静かつ具体的な要求を伝えることが基本です。
感情的にならず、証拠を提示しながら理論的に主張しましょう。交渉の際も記録は必ず残しておくことがおすすめです。
必要に応じて、専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズに解決へと進むことが可能です。
\27,500円から弁護士に依頼できる!/
退職代行の利用時に給料が受け取れるのか?


未払い給料がなくても退職代行の依頼をする際、「給料はきちんと支払われるの?」という不安を感じる方もいます。
代行業者に依頼した場合には会社との直接のやり取りがなくなるため、給料の支払いの流れが不透明に感じるのも無理はありません。
ここでは、給料の支払いの仕組みや注意点について具体的にご説明していきます。
退職時の給料の支払いの流れ
退職の際、原則として未払いの給料は最終出勤日の翌月末までに支払われるのが一般的です。
ただ、会社の規則や支払タイミングによって異なるため、給与規定を確認することが大切です。
退職代行を通じて辞める場合でも、会社には支払い義務がありますので、基本的な流れに変わりはありません。
給料の支払いに関する主なリスク
退職代行を利用することで、会社側が一方的に連絡を絶つ事例もゼロではありません。
そうなると、未払い給料の請求が滞るリスクがあります。
また、契約内容や雇用形態によっては、退職理由が争点となることもあるため、リスクを見越した対応が求められます。
依頼前の給料確認のポイント
未払い給料の場合と同じく、退職代行を依頼する前には、給与明細や契約書の内容を確認しておくことが重要です。
特に残業代や手当が適正に計算されているか、自分の勤務記録と相違がないかを見直しておきましょう。
退職時の支払い条件や損害賠償に関する条項などもきちんとチェックすることが大切です。



情報を事前に把握しておくことで、万が一の未払いの際にも冷静に対応できます!
退職代行サービスの基本概要


退職代行サービスは、退職を希望する労働者に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。
「自分では言い出しにくい」「会社側が強く引き止めてくる」など、スムーズな退職が困難な状況において、第三者を介することで安全かつ迅速に退職が実現できます。
心理的負担を軽減しながら、法律に則って適切に手続きを進めることが可能で、依頼する業者によっては、残業代や未払い給料の交渉サポートなども含まれます。
法律事務所が運営するサービスであれば、弁護士が直接介入できるため、法律問題への対応などより法的に強い立場での対応が可能です。
利用の流れとしては、まずは電話やメールで代行業者に相談します。
その後、ヒアリングを通じて状況を確認し、契約が成立すると最短で即日対応も可能です。
業者が会社に退職の意思を伝え、退職届の提出や私物の返却など、必要な手続きが進められます。



退職完了までサポートが続くため、ご本人が直接やり取りをすることなく退職できます!
利用時の注意点とチェックリスト


退職代行を安心して利用するには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
信頼できる業者を選び、事前に自分の状況を整理することで、トラブルのリスクを大幅に軽減できます。
ここでは、事前確認すべきポイントや利用時の注意点について整理します。
利用前の事前確認ポイント
まず確認すべきは、退職代行業者のサービス内容です。
対応範囲や実績、サポート体制などを把握しておくことで、依頼後の不安を軽減できます。
自分の勤務状況や未払い給料の有無についても整理しておくと、よりスムーズな対応が可能になります。
信頼できる退職代行業者の見極め方
業者を選ぶ際には、口コミや評価だけでなく、実際の対応実績や運営母体の信頼性を確認しましょう。
「弁護士や労働組合が関与しているか?」どうかも重要な判断材料です。



信頼できる業者を選ぶことが、安心して依頼するための第一歩となります!
料金体系と追加費用の確認
サービスの料金は業者によって異なります。
基本料金の他に追加費用が発生するケースもあるため、契約前に詳細を確認することが必要です。
未払い給料の回収サポートがオプションとなっている場合には、その費用も見積もっておきましょう。



「回収費用から◯割を支払う」などが明記されています!
リスクヘッジのための事前相談
実際に依頼する前に、無料相談を活用して不安点を解消することをおすすめします。
専門家の意見を聞くことで、自分のケースに合った対応方法が見えてきます。
あらかじめ疑問点をリストアップしておくと、相談がより有意義なものになるでしょう。



相談時の対応によって、業者側のサポート体制や姿勢も見えてくるので、業者選びの参考にも!
退職代行利用時の未払い給料について:まとめ
この記事では、退職代行を利用した場合の未払い給料を取り戻す方法や注意点などについて解説してきました。
未払いだった給料は退職代行サービスを利用しても取り戻すことができます。
しかし、取り戻すためには勤務していたことを示す証拠、就業規則や時効の確認など事前の準備も必要です。
また、その際に法的な手続きが必要となることもあり、弁護士が提供する退職代行サービスを選ぶことが最も確実です。
この記事で紹介した手順や注意点を参考に、事前に情報を整理し、信頼できる業者を選びましょう。
そして、疑問点があれば専門家に相談することで、より安心して退職の手続きを進めることができます!