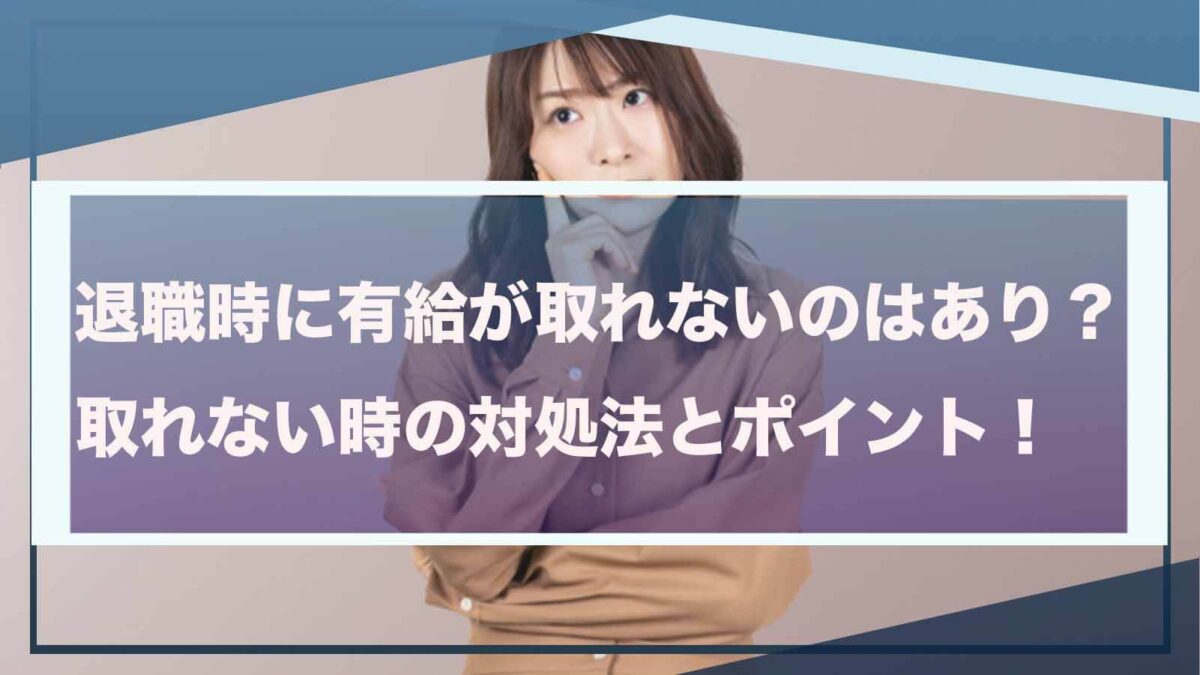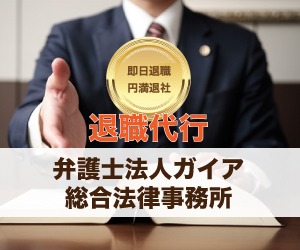- 退職時に有給が取れない理由
- 退職時に有給が取れない時の対処法
- トラブルなく消化するためのポイント
「退職時には有給を全て使ってから辞めたい」という方も多いでしょう。
しかし、上司や会社側に勇気を振り絞って伝えても、「人手不足だから」などの理由で有給を使いきれないこともめずらしくありません。
有給が使いきれなければ金銭的に損をするだけでなく、転職活動に遅れが出ることも予想できるので、可能なら全て消化してから辞められるのがベストです。
そこでこの記事では、退職時に有給が取れないのはありなのかの真偽から、拒否された場合の対処法、トラブルなく消化するためのポイントなどについて解説していきます。
\退職成功率100%中!!/
「退職時に有給が取れない」のは基本的になし!

有給休暇の取得について、会社の許可は不要です。
つまり、労働者が有給休暇を申請し、それが労働基準法に基づいて適切である限り、会社側は拒否できません。
特に退職時には有給消化を申し出るケースが多いですが、会社側がこれを拒否するのは違法になります。
基本的に有給は自由に使える
有給休暇は条件を満たしていれば、正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく取得できるものです。
これは労働基準法39条1項で定められているので、基本的にはご自身が使いたい時に自由に取得できます。
ですので退職前だとしても有給を消化することは可能です。
退職時の有給休暇の買取
会社側がどうしても有給休暇の取得を認められない場合、会社が残っている有給休暇を買い取る形で補償することもあります。
しかし、これも義務ではなく会社の方針に依存するため、事前に確認することが重要です。
時季変更権には注意が必要
会社側には「時季変更権」というものが認められています(労働基準法39条5項)。
これは、『事業の正常な運営を妨げる場合に有給の取得期間をずらせる』というものです。
例をあげると、繁忙期などの重要な時期に従業員全員が有給を使ってしまえば会社の経営に大ダメージが出てしまいます。
こういった時に会社側に与えられた権利です。
 SUSUMU
SUSUMU退職日が決まっていて「今有給消化するしかない」といった状況では、”時季変更権より有給消化の方が優先される”点は覚えておきましょう!
転職先が決まっている場合は開始日も確認しておく
有給休暇中は現在の会社での在籍期間に入ります。
そのため、休み中だからといって転職先で働き始める場合には注意が必要です。
二重就労は、会社の就業規則違反や雇用保険の問題にも関わり、最悪の場合どちらの会社も懲戒解雇になる可能性もあります。



有給期間中に働き始めたい場合には、現在の会社と転職先への相談と就業規則の確認をきちんと行いましょう!
会社が退職時に有給を取らせてくれない理由


退職時に有給休暇を申請しても、会社側から断られるというケースは意外と多く見られます。
ただ法律上では、有給の消化は拒否できないことが決められています。
「では、なぜ会社側は拒否をしてくるのでしょうか?
その背景には、企業の都合や制度の誤解が存在しています。
- 業務繁忙による人手不足
- 引き継ぎ期間の不足
- 有給申請のタイミング不一致
- 権利に対する無理解や意図的な拒否
- コストや負担を避けようとしている
- 反論してこないと思われている
- 後任がまだ見つかっていない
- まだ有給をもらえる条件になっていない
業務の引継ぎや人手不足
会社側としては、退職時に従業員が有給を取ると、業務の引き継ぎや後任の手配に支障が出る可能性があります。
特に繁忙期や重要なプロジェクトの時期には、退職者の抜けた穴をすぐに埋めることが難しくなりがちです。
そのため、有給を申請しても認めたらがなくなってしまします。
ただ、「労働者には有給休暇を取得する権利」が法律で保障されているため、会社側は本来、拒否することはできません。



有給の拒否は特に中小企業にその傾向が高いです!
引き継ぎ期間の不足
退職日が近づいているにもかかわらず、業務の引き継ぎが終わっていないことを理由に、有給取得を拒まれるケースもあります。
この場合、有給期間中に連絡可能な体制を整えることで業務支障のリスクを減らすことができます。
事前にスケジュールを共有し、計画的な引き継ぎが重要です。
有給申請のタイミング不一致
有給休暇の申請は、社内規定に基づいて早めに行う必要があります。
特に繁忙期や直前の申請は、会社側の「時季変更権」により変更を求められる可能性があります。
退職が決まり次第、早めに取得希望日を伝えることが得策です。
この時季変更権も”取得期間をずらせる”というものなので、退職日ギリギリならその効力はありません。



ただ、円満な退職を望むなら会社や上司に対して強気に出るのは難しいです!
有給休暇の権利に対する無理解や意図的な拒否
上司や会社側が有給休暇の取得に関する社内ルールや就業規則を把握していない場合、誤解が生まれやすくなります。
申請ルールや取得制限が文書で定められていることが多いため、事前に確認してから行動に移すことで不要なトラブルを回避できます。
また、会社によっては有給取得自体に厳しい姿勢を示し、法律違反スレスレの行動をとることもあります。
会社側のコストや負担を避けようとしている
有給休暇中に支払われる給与は、会社にとってコストになります。
業績悪化などの理由から、有給取得を経営的に避けたいと考える企業も存在します。
人件費の抑制を目的とした拒否は、場合によっては法的問題に発展する可能性があるため、慎重な対応が必要です。



退職代行などの第三者へ依頼する場合には、依頼先によって有給取得の交渉も可能です!
反論してこないと思われている
外国に比べ、日本の有給取得率はかなり低くなっています。
そのため転職を経験した方の中には、有給を消化しきる前に退職したケースもめずらしくありません。
会社側の考えとしても「こちらが拒否すれば諦めるだろう」と考えている企業も多いです。
特に日常的に労働環境が悪いブラック企業の方がこうした意識が強く出てきます。
また、上司によっては有給休暇のルールさえ把握していない人物もいます。



泣き寝入りしないためには、『人事や労務に相談する』『弁護士や退職代行へ依頼する』ことも考えましょう!
後任がまだ見つかっていない
様々な原因から後任が決まっていない場合にも、有給を消化させてくれないことがあります。
後任選びは会社の責任ではありますが、退職が決まっている方の中には気を使って有給を諦める方も多いです。
引き継ぎ資料や業務マニュアルを制作することである程度は回避が可能ですが、会社からの引き止めが強い場合には弁護士や退職代行へ相談すると良いでしょう。
まだ有給をもらえる条件になっていない
有給消化を拒否される原因として、ご自身が有給を取得できる条件をクリアしていないケースもあります。
有給休暇を取得するには次の2つの条件を満たすことが必須です。
- 入社から6ヶ月の継続勤務
- 全労働日の8割の出勤



新卒や中途など入社から間もない方は「まだ有給が付与されていなかった」こともあるので、退職を考えている方は注意しましょう!
\退職成功率100%中!!/
退職時に有給が取れない時の対処法7選


有給申請を断られたまま退職日を迎えると、本来得られるべき休暇と給与を失ってしまう恐れがあります。
有給休暇は法律上で認められた労働者の権利です。
ここでは、社内での交渉から外部機関の活用、退職代行サービスの利用まで、段階的な対処法を詳しくご紹介します。
- 会社の規則を確認する
- 上司への再交渉と根拠提示
- 有給を買い取ってもらう
- 上の役職か人事に相談する
- 労働基準監督署に相談
- 弁護士に相談する
- 退職代行サービスを依頼する
会社の規則を確認する
会社の就業規則や労働契約書に有給休暇に関する規定が明記されている場合、これを確認し、有給を取らせない理由が正当かどうかをチェックします。
場合によっては、会社の規定が違法な可能性もあります。
上司への再交渉と根拠提示
規則の確認を終えたらまずは、直属の上司に再度有給取得の意思を伝えるところから始めましょう。
ポイントは、「感情的に主張するのではなく、労働基準法や社内規定をもとに理論的に説明する」ことです。
可能であれば、代替業務の引き継ぎ案などもあわせて提示すると、より協力を得やすくなります。



忙しそうな時間ではなく、相手が落ち着いて話せる時間帯を選ぶことで、スムーズなやり取りが期待できます!
有給を買い取ってもらう
有給の消化が難しい場合、会社に有給休暇分の給与を買い取ってもらうことも検討できます。
これを「有給休暇の買い取り」といい、会社によっては対応してくれる場合があります。
ただし、これは法的に義務付けられていないため、交渉が必要です。
上の役職か人事に相談する
有給を許可する上司から拒否された方は、そのさらに上の役職の人間か人事部に相談してみましょう。
上司が変な考えを持つ人物だったとしても会社全体がブラックとは限りません。
また、有給の取得申請の際は、口頭だけでなく必ず書面やデジタルで記録を残しましょう。
メールや社内システムを通じて、「いつ誰にどのような申請を行ったか?」を明確にします。
上司や人事からの返信も保存し、必要に応じてスクリーンショットを撮っておくのがおすすめです。



証拠があれば、状況説明もしやすく、後のトラブル時にも有利に運ぶはずです!
労働基準監督署に相談
社内での解決が難しいと感じたら、地域の労働基準監督署に相談するという選択肢もあります。
労基署は公的な機関になるので、無料で相談にのってくれます。
匿名での相談も可能で、現状を伝えることでアドバイスや指導が得られます。
さらに必要に応じて会社に対する是正勧告が行われることもあります。
ただし、違反が見つかったとしても立ち入り調査や指導といった対応になるため、「有給が使えるようになる!」とは限りません。
弁護士に相談する
費用がかかってもしっかりと解決したい方は弁護士に相談や依頼しましょう。
弁護士なら代理人としてご自身に代わって交渉が行えますし、肩書きから会社側がすんなりと合意してくれる可能性もあります。
退職代行を展開する弁護士事務所なら、「退職の代行+有給消化」で5万円ほどから依頼できます。
退職代行サービスを依頼する
上記の方法でも状況が改善しない場合、退職代行サービスを利用する選択肢があります。
代行業者があなたに代わって会社と連絡を取り、有給消化を含めた退職手続きを代行してくれます。
対応実績や費用体系をしっかり比較した上で、信頼できる業者を選ぶことが、精神的な負担軽減につながります。
有給取得に関する交渉をするには、弁護士や労働組合が運営する代行サービスに依頼する必要があります。



民間でも、交渉が必要な際に提携している労働組合にバトンタッチする業者も!
\退職成功率100%中!!/
退職時にトラブルなく有給を消化するポイント6選


会社を辞める日が決まっていたら、「最後まで円満に退職したい」と考える方も多いでしょう。
スムーズに有給を消化するためには、事前準備と記録管理が欠かせません。
退職時のトラブルを防ぐためにも、段階的に対策を講じることが重要です。
ここでは、安心して有給を取得するための具体的なポイントを解説していきます。
- 退職日の1~2ヶ月前からの計画的申請
- 上司と有給について話し合っておく
- メールと社内システムによる二重申請
- こまめに有給を使っておく
- 引き継ぎ終了後にまとめて消化する
- 専門家や退職代行サービスの事前情報収集
退職日の1~2ヶ月前からの計画的申請
退職が決まったら、できるだけ早めに有給の申請を進めることが大切です。
理想的には退職日の1~2ヶ月前に希望日程を提示し、会社側に十分な調整時間を確保してもらいましょう。
早めに申請を出すことで、繁忙期などを理由にした取得拒否のリスクを軽減できます。



余裕を持ったスケジュールは引継ぎの準備にも有利に働きます!
上司と有給について話し合っておく
円満退職を望む方は、あらかじめ上司と有給についての相談をしておくとトラブルがかなり減ります。
「有給を全て消化して辞めたい」という希望があるように、上司も「この日までに後任選びや引き継ぎを終わらせたい」などのスケジュールを考えています。
また、有給を消化している間に緊急の連絡が必要になるケースも考えられます。
そのため、有給取得前に上司・会社側と連絡手段や対応可能な時間帯について取り決めておくとスムーズです。
「必要な連絡はメールか電話か?」「どの時間帯なら対応可能か?」などを明確にすることで、会社側も安心し、トラブルを未然に防ぐことができます。



なるべく早い段階で有給消化の話し合いを行っておくと良いでしょう!
メールと社内システムによる二重申請
有給申請は、社内の勤怠システムだけでなく、直属の上司や人事担当者にメールでも同時に申請内容を伝えるのが効果的です。
二重で申請を行うことで、申請漏れや伝達ミスといったリスクを避けられます。
さらに、メールでのやりとりは記録として残るため、万が一トラブルが起きた場合でも正当性な証拠として活用できます。
申請後のやり取りや承認の連絡などは、スマホやパソコンなどにスクショしておくのもおすすめです。



記録をクラウドに保管しておけば、必要なときにすぐに提出できます!
こまめに有給を使っておく
退職時のまとまった有給消化に抵抗を感じている方は、引き継ぎを行いつつ小まめに消化していくのもオススメです。
一般的な企業では退職日の1〜3ヶ月前には上司や会社に報告を行います。
普通の会社ならこの期間中で新しい業務が増えることはないでしょう。
そのため、「引き継ぎをしつつ有給を消化していく」にはちょうど良い時間になります。
引き継ぎ終了後にまとめて消化する
最後が後任選びの完了や引き継ぎがしっかりと終わるまで有給を取らない方法です。
この方法は会社から見れば感謝されるでしょう。
しかし、有給がかなり残っていると「消化しきれない」「転職先が見つからなかった」という事態に陥る可能性もあるのでご注意ください。
専門家や退職代行サービスの事前情報収集
仮に会社との交渉が難航した場合に備えて、労基署や弁護士、退職代行サービスについて事前に調べておくと安心です。
相談窓口の場所や連絡先、費用、対応内容などを把握しておくことで、いざという時にも落ち着いて対応できるでしょう。



情報収集は早い段階から始めるのが理想的です!
退職代行サービスを利用するメリットと選び方


自分で有給取得の交渉が難しいと感じた場合には、退職代行サービスの利用を検討する必要があります。
第三者の専門家に任せることで、ストレスやトラブルを避けながらスムーズに退職することが可能です。
退職代行で有給取得交渉は可能か
退職代行業者の中には、有給取得の交渉まで代行してくれるところがあります。
ただし、交渉の範囲には法的な制限があり、労働組合や弁護士が運営するサービスでないと、法律上の交渉はできないません。
依頼前には、自分の希望するサポートが可能かを明確に確認しておくことが大切です。



民間でも交渉が必要な際に提携先の労働組合に任せる方法を取るサービスもあります!
サービス選びのチェックポイント
退職代行サービスを選ぶ際には、料金体系や対応実績、サポート体制を細かく確認しましょう。
対応可能な業務の範囲をはじめ、対応時間帯や口コミの評価など、事前に把握することで自分に合った業者を見極めやすくなります。
また、実際の利用者の声を参考にするのも効果的です。
とはいえ、退職代行に限らずレビューには、満足できなかった方からの意見が強く反映されがちです。



”あくまでも参考程度”と考え、冷静に業者選びを行いましょう!
トラブルを防ぐ契約時の注意点
業者と契約を結ぶ際には、契約書の内容をしっかりと読み込み、重要な項目に抜け漏れがないかを確認してください。
「こんなはずでは、、、」とはならないためにも、返金保証の有無やアフターフォローの内容についても事前に把握しておくと安心です。
契約書に記載されている内容が自分の希望と一致しているかを確認することがトラブル回避につながります。
退職代行サービスの利用の流れ


初めて退職代行を利用する方にとって、手続きの流れを理解することは安心材料になります。
ここでは、問い合わせから退職完了までの一般的なステップをご紹介します。
無料相談と見積もり取得
まずは業者の公式サイトやメールなどで無料相談を行い、自分の状況や希望を伝えます。
そのうえで見積もりを出してもらい、料金や対応内容について納得した上で次のステップに進みます。
相談時には、「有給取得の交渉が可能かどうか」もきちんと確認しておくと良いでしょう。
正式依頼~契約手続き
サービス内容に納得できたら、契約書に署名・捺印し、正式に依頼します。
支払い方法は銀行振込やクレジットカードが一般的で、領収書の発行も依頼可能です。
契約締結後、速やかに手続きが始まるので、必要な書類などは事前に準備しておきましょう。
退職日までのサポート内容
退職代行業者は、退職の意思表示から会社とのやりとり、業者によっては有給取得の交渉まで代行してくれます。
連絡の内容や進捗は依頼者に報告されるため、状況を把握しながら安心して任せられます。
会社との直接交渉に不安がある方でも、サポートがあれば安心して退職に臨めるでしょう。
退職時に有給が取れないことについて:まとめ
この記事では、退職時に有給が取れない場合の真偽から拒否された際の対処法、トラブルなく消化するポイントなどについて解説してきました。
有給休暇は労働者に与えらえた権利です。
ですので、退職時であっても会社や上司が「有給消化を拒否する」といったことはできません。
ただ、退職を控えた状態で会社とのトラブルは避けるべきです。
退職時に有給を消化できない状況に直面した際には、まずは社内交渉から始め、記録の保全や外部への相談を通じて段階的に対処していくことが大切です。
どうしても解決できない場合には、退職代行サービスのような第三者の活用も視野に入れましょう。
安心して退職を迎えるためには、情報収集と早めの準備が鍵となります!