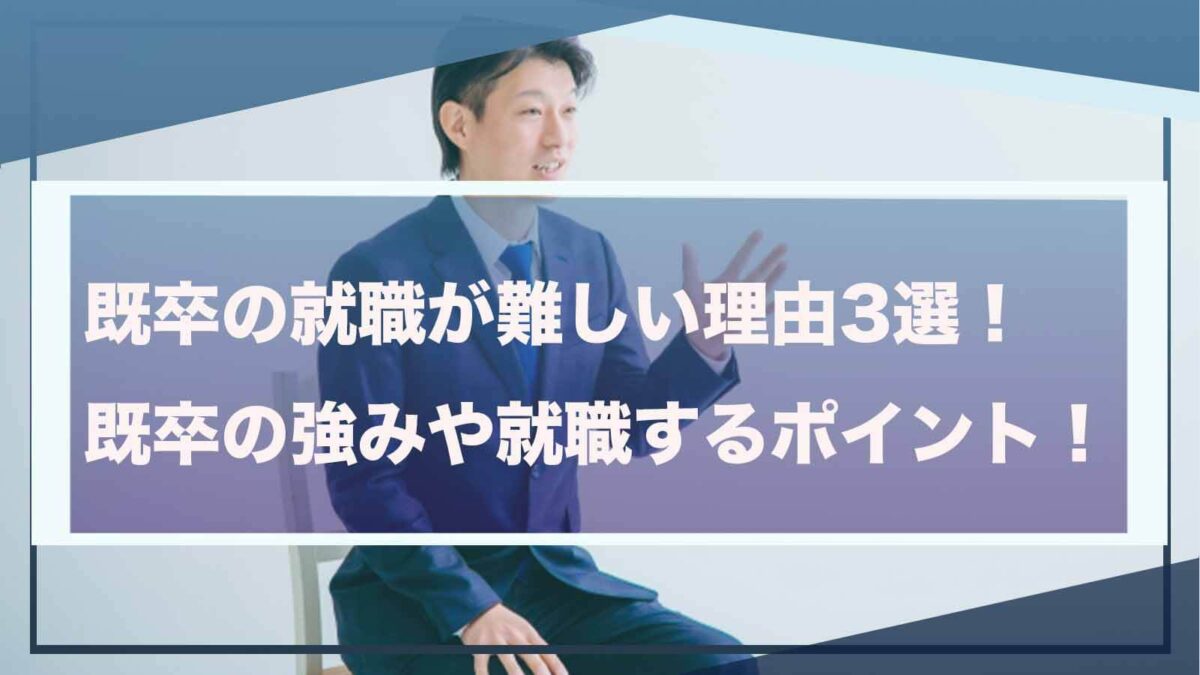- 既卒の就職が難しいと言われる理由
- 既卒が就職する方法
- 既卒が就職を成功させるポイント
- 既卒が就職する時の注意点
いろいろな理由から学生時代に就職ができなかった方は大勢います。
その中には「これから正社員を目指したい!」という方もいるでしょう。
しかし、ネットなどを見ていると”既卒の就職は難しい”という言葉が書かれていることがあります。
ですが結論から言って『既卒の方でも就職することは可能』です!
そこでこの記事では、既卒の就職が難しいと言われる理由から、既卒者の強み、就職を成功させるポイントなどについて解説していきます。
そもそも既卒とは?定義や新卒・中途との違い

既卒という言葉だけを聞くと「新卒でもなく、中途でもない特殊な立場」と感じる方もいるでしょう。
まずは、既卒の定義を明確に把握し、”自分がどのカテゴリーに該当するのか?”を整理してみましょう。
ここをはっきりさせることで、就職活動の方向性も定まり、企業にも納得感を持ってアピールしやすくなります。
既卒とは何か?
既卒とは、「学校(大学・専門学校・高専など)を卒業後、卒業年度の就職活動に応募しなかった、または応募したものの内定を得られず、その後も就職していない人」を指します。
言い換えれば、『卒業後一度も就職経験がない社会人未経験者』という位置づけです。
なお、卒業年度を含めて3年以内であれば、既卒として扱われるケースが一般的です。
新卒・中途との違い
新卒は卒業年度に就職活動を行う人、中途は社会人経験がある人を指しますが、既卒は「新卒期を逃した」または「就職活動をしなかった」人です。
企業側から見ると、「まだ社会経験がないが、応募時期を逃した」という特有のイメージがつきまとうため、応募書類や面接でしっかり状況説明をする必要があります。
 SUSUMU
SUSUMUせっかく面接まで進んでも、不安を拭いきれずに採用見送りになることも!
既卒の就職が難しいと言われる理由5選


既卒の方でも正社員として就職することは可能です。
しかし、新卒の方に比べた場合、既卒者ならではのハードルがあり、難易度が高くなるのは事実です。
企業側は新卒と同じ枠組みで評価しづらく、一方で中途採用枠を設けても経験値が足りないと判断されやすいのが実情。
ここでは、「なぜ既卒の就職が難しいと言われるのか?」、その主な理由を整理していきましょう。
- 長期ブランクによるスキル・知識の陳腐化
- マイナスイメージを持たれる可能性が
- 日本での就職は新卒の方が有利
- 中途枠で採用されるのも難しい
- 競争相手の増加と求人数の不均衡
長期ブランクによるスキル・知識の陳腐化
既卒者は卒業後から就職までの間に空白期間が生じるため、その間に学んだ専門知識やスキルが古くなっていると見られがちです。
特にITやWeb業界など、技術トレンドの変化が激しい分野では、「最新の知識を持っていない」と判断されるリスクが高まります。
企業側は即戦力としての期待をしにくく、再度基礎から育成する手間を懸念することも。



既卒者は「ブランク中に何を学んでいたか?」を具体的にアピールする必要があります!
マイナスイメージを持たれる可能性がある
既卒者の就職が難しいと言われる1番の理由は、企業側からマイナスイメージを持たれる可能性が高いからです。
そのマイナスイメージとしては次のようなものがあげられます。
- 何か問題を抱えている
- 行動力がない
- 働く意欲がない
こうしたイメージを勝手につけられてしまうと、選考中に落とされてしまう原因になってしまいます。



既卒になった原因がある方は、まずはそのことを説明できるようにしておきましょう!
日本での就職は新卒の方が有利
多くの企業は年度単位で新卒採用を計画しており、どうしても新卒枠の方が有利です。
新卒の方が、年齢の若い新卒者の方が会社に馴染みやすく、教育もしやすいのが理由だと考えられます。
既卒者はその枠を外れるため、新卒向けのエントリーシートや面接の機会を逃してしまいます。
結果として、採用枠そのものが少ない「既卒枠」「中途枠」で応募せざるをえず、”そもそもの選択肢が限られて”しまいます。



求人自体が少ない分、倍率が高くなりやすいのも難易度を上げる要因です!
中途枠で採用されるのも難しい
中途採用では基本的に社会人経験を伴う即戦力を求める企業が多いため、既卒者は「社会人経験がゼロ」という点で敬遠されることがあります。
企業側から見ると、同じ中途枠に応募する候補者と比較してスキルや業務理解度が浅いと判断されやすいのが実情です。
結果として、未経験可求人にしか応募できないケースが増え、希望職種や業界の幅が狭まる傾向があります。
これにより、自分の適性に合った求人が限られ、就職活動が長期化しやすくなるのです。
競争相手の増加と求人数の不均衡
少子化が進む一方で大学卒業者数そのものは依然として多く、卒業後も就職できていない既卒者の数は増加しています。
つまり、限られた既卒枠を多数の応募者で奪い合う状況になっているのです。
加えて、多くの企業が採用コストの削減や効率化の観点から、新卒一括採用を続ける傾向があるため、既卒者向け求人は相対的に少なくなっています。



「需給バランスの不均衡が、既卒の就職難をさらに助長している」とも言えます!
既卒者が就職を成功させるポイント10選


既卒の就職は確かにハードルがあるものの、適切な準備と戦略があれば十分に成功可能です。
ここでは、既卒者が採用内定を勝ち取るための具体的なステップやポイントをまとめました。
転職活動をしたことがない方でも真似しやすいよう、順を追って解説していきます。
- 自己分析をしっかりとする
- 企業研究を欠かさずに志望動機を練り込む
- ブランク期間の取り組みをアピールする
- 書類選考での見せ方を工夫する
- 模擬面接やロールプレイで伝え方を磨く
- インターンシップやボランティアで実践経験を積む
- 自分ひとりで就活を行わない
- なるべくすぐに行動する
- 求人の幅は広く探す
- メンタルケアとモチベーション維持を意識
自己分析をしっかりとする
社会人経験がない分、学生時代の活動やアルバイト、ボランティアで培ったスキルや価値観を深掘りして整理しましょう。
自己分析を通して、面接や書類作成で「 自分が企業にとってどのような価値を提供できるか?」を明確に伝えられます。
特に既卒者は経験不足を補うために、自分のポテンシャルや学習意欲を前面に出すことが重要です。



具体的なエピソードを用意しておくと説得力が高まります!
企業研究を欠かさずに志望動機を練り込む
企業が求める人材像や社風、ビジョンを深く理解することで、志望動機の説得力がアップします。
自分の価値観やキャリアビジョンと企業の方向性をリンクさせ、「なぜここで働きたいのか」を明確に表現しましょう。
既卒者の場合、単に「興味があるから!」ではインパクトが弱いため、具体的な事業内容や社内環境を挙げて応募先を選んだ理由を示すと効果的です。
こうした準備があると、面接官に本気度を感じてもらいやすくなります。
ブランク期間のポジティブな取り組みをアピールする
既卒の場合、企業側からマイナスのイメージを持たれることもあります。
既卒として評価されるためには、卒業後のブランクを「何もしていなかった」期間ではなく「自己成長に充てた」期間として示すことが大切です。
例えば、語学学習やプログラミングスクールへの通学、資格試験の勉強など、具体的な行動をアピールしましょう。
ブランク中に得た成果やスキルを数値化できれば、企業にとっての価値がより伝わりやすくなります。



「学習意欲が高く、自ら行動できる人材」という印象を与えられます!
書類選考での見せ方を工夫する
履歴書や職務経歴書では、学歴や資格・スキルだけでなく、学生時代の成果やアルバイト経験、インターンシップでの実績を強調しましょう。
ブランク期間がある場合は、「自己啓発に取り組んだ」「業界研究を行った」などの項目を作り、前向きなアクションを示すことが重要です。
自己PR欄には、自分の強みとそれを裏付けるエピソードを具体的に記載すると好印象を得られます。
特に数字で示せる成果があれば、説得力が格段に上がります。
模擬面接やロールプレイで伝え方を磨く
面接では、既卒者としての立ち位置を正しく説明できるかどうかがポイントになります。
模擬面接を通じて「ブランク期間の説明」「志望動機の論理展開」「自己PR」の伝え方を何度も練習しましょう。
友人やキャリアアドバイザーにフィードバックをもらい、自分が話す印象や論理の一貫性をブラッシュアップすることで、本番で自信を持って受け答えができるようになります。
声の大きさや話す速度、アイコンタクトといった非言語コミュニケーションも意識して練習することが有効です。



練習風景をスマホなどで録画し、確認するのも効果的です!
インターンシップやボランティアで実践経験を積む
既卒期間中に業界関連のインターンシップやボランティアに参加し、実務に近い経験を積むことで、企業側の評価も高まります。
短期のインターンでも、実際の職場環境や仕事の進め方を体感できるため、面接で「即戦力になれる可能性」を具体的に示せる材料になります。
また、インターン先での人脈づくりも就職活動に役立ち、推薦や求人紹介につながることも。



短期間でも企業で働くことで、内部の雰囲気や環境をチェックできます!
自分ひとりで就活を行わない
既卒の方の就職では、自分ひとりだけで活動しない方が良いこともあります。
就職サイトやエージェントだけでなく、OB・OG訪問や業界セミナー、交流会などに積極的に参加して情報を集めましょう。
人脈を通じたリアルな情報は、求人票に載っていない企業の雰囲気や実際の働き方を知る上で非常に貴重です。
特に既卒者の場合、経験不足を補うために「企業文化にマッチするか?」を早めに見極めることが大切です。
直接話を聞くことで、面接時に使える具体的な企業理解を得られるだけでなく、書類選考での志望度をアピールする材料にもなります。
なるべくすぐに行動する
「既卒で就職したい」という方は、早め早めな前向きな行動が鍵になります。
すぐに行動に移せれば、年齢が若いうちに多くの会社に応募できます。



面接に苦手意識があったしても、場数を踏んでいけば自然と上手くなっていくはず!
求人の幅は広く探す
既卒の方の場合、応募する企業の条件に制限をかけすぎるのはよくないでしょう。
もちろん「どこでも内定をもらえれば良い」というわけではありませんが、チャンスを多くするためにも求人の幅は広く探していく方が良いです。
メンタルケアとモチベーション維持を意識する
既卒での就職活動は思い通りに進まないことも多く、落ち込みやすい場面もあるでしょう。
定期的に自分の目標やキャリアビジョンを振り返り、進捗を可視化することで、モチベーションを維持しやすくなります。
また、悩んだときにはキャリアカウンセラーや信頼できる友人に相談し、精神的なサポートを得ることも重要。
心身の健康を保ちながら就活を継続できる環境づくりが、内定獲得までの継続力を支えます。



きちんとした睡眠時間の確保やバランスの良い食事、適度な運動ももちろん大事です!
既卒者が就職するときの注意点


既卒者が就職活動を行う際にはいくつか注意すべきポイントがあります。
これらを押さえておかないと、せっかく書類選考を通過しても面接で落とされるリスクが高まります。
次の注意点を事前に理解し、万全の準備を整えましょう。
- 空白期間の具体的な説明を必ず用意
- 志望動機は他社と差別化された内容にする
- 積極的に自己PRで学び続ける意欲を示す
- ネガティブに考えない
- 就活には期限を決める
- マナーや話し方に気を付ける
- 情報収集は複数の媒体・手段を使い分ける
空白期間の具体的な説明を必ず用意する
企業は既卒者のブランクに強い関心を寄せるため、「何をしていたのか?」を詳細に説明できなければ内定を得るのは難しいでしょう。
旅行や趣味だけで過ごした場合でも、そこから得た気づきや学びを整理して伝えることが大切です。
特にスキル習得や資格取得のために行った勉強など、ポジティブな取り組みを示すことでマイナスイメージを減らせます。



説明に一貫性があると、面接官に信頼感を持ってもらいやすくなります!
志望動機は他社と差別化された内容にする
企業にアピールする際、志望動機が「なんとなく」「知名度があるから」では弱い印象を与えます。
企業の事業内容や社風を調べた上で、自分の強みやキャリアビジョンと結びつけたオリジナルの志望理由を作成しましょう。
特に既卒者は経験不足を補うために、「なぜこの会社でなければならないのか?」を強く訴える必要があります。
具体的なエピソードや数字を示すと、採用担当者に与える印象が格段にアップします。
積極的に自己PRで学び続ける意欲を示す
既卒者は経験不足を補うために、自己PRで「学習意欲が高い」「挑戦してきた」ことをアピールしましょう。
何もしてこなかった印象を与えないために、ブランク期間中の学びや取り組みを具体的な成果とともに示すことがポイントです。
たとえば、「オンライン講座でTOEICの点数を○○点向上させた!」「独学でプログラミングの基本を身につけた!」など、数字で裏付けられる実績を用意しておくと説得力があります。
こうしておけば、企業側は「学び続ける姿勢がある」と判断しやすくなります。
「既卒」ということをネガティブに考えない
既卒者の中には、
「自分は学生時代に就職できなかったから上手くいかないだろう・・・」
「周りに比べて劣っている・・・」
などと考えている方もいるかもしれません。
しかし就職したいと望んでいるなら、こうしたネガティブな考えは早めに捨てた方が良いです。
どんなに過去を後悔しても今の状況を変えることはできません。



プラス思考で考える人の方が、マイナス思考より採用される可能性も高くなります!
就活には期限を決める
既卒者の就活では、期限を決めて活動していくことをオススメします。
アルバイトで生計を立てていると自由にできる時間が多い反面、どこまで時間を使って就職するかが曖昧になる方も多いです。
確かにじっくりと企業を選んで就活していくことは大切です。期限を決めていかないと、ダラダラと時間を使っていくだけになってしまいます。
- 「◯月までに就活を終える」
- 「今年中には応募先を探す」
といった具体的な目標を持って就職活動をしていきましょう。
面接ではマナーや話し方に気を付ける
面接の際にはマナーや話し方にも細心の注意をはかりましよう。
アルバイトなどであれば、多少、マナーや言葉遣いが乱れていても許してもらえる場面もあるでしょう。
ですが正社員なら、既卒者であっても面接時には新卒と同等のビジネスマナーが求められます。
清潔感のあるスーツやビジネスカジュアルを選択し、髪型や靴まで細部に気を配りましょう。
面接会場に到着したら、受付での一礼や待合室での態度、面接終了後のお礼メールなど、基本的マナーを欠かさないことが重要。
マナーの徹底は、「社会人経験がなくても基礎的素養は備わっている」という好印象につながります。



模擬面接などを通して、実際の面接で失礼な場面を作らないようにしましょう!
情報収集は複数の媒体・手段を使い分ける
既卒者向け求人は、新卒や中途に比べて限られているため、就職サイトだけでなく、転職エージェントやハロワ、SNS、セミナーなど複数のチャネルを活用しましょう。
特にエージェントを利用する場合は、「既卒歓迎」「未経験可」などのキーワードで検索すれば、自分に合った求人を効率的に探せます。
また、企業説明会や業界セミナーに参加してリアルな情報を得ることも重要です。



情報の偏りを防ぎ、多角的に求人や企業を比較検討することで、ミスマッチを防ぎやすくなります!
企業から抱かれやすい既卒者へのイメージ


企業は応募者を判断する際、履歴書や面接で伝わる印象を重視します。
既卒者に対しては、どうしても「社会人経験がない」「スキルが不足している」といったイメージがつきまといがちです。
ここでは、企業が既卒者に対して抱きやすい代表的なイメージを解説し、どうカバーすべきかを考えます。
社会人マナーやビジネスマナーへの不安
既卒者は社会人経験がないため、初対面での挨拶や敬語の使い方、メールの文面など、「基本的なビジネスマナーが備わっていないのではないか?」と懸念されます。
企業側は採用後すぐに仕事を任せられる即戦力を求めることが多く、マナー研修に時間やコストをかけにくいのが実情です。
そのため、面接時には最低限の社会人マナーを徹底し、丁寧に対応することが重要です。



事前にビジネスマナー講座を受講するなどして、”即戦力として力を発揮できる”印象を示しましょう!
モチベーションや本気度への疑念
「なぜ卒業後すぐに就職活動をしなかったのか?」の理由を企業は強く意識します。
「働く意思が本当にあるのか?」「長続きするのか?」といった疑念を払拭しないと、面接を通過するのは難しいでしょう。
特に既卒期間が長引いている場合、「就職に対する本気度が乏しいのでは?」と判断されがちです。
自己分析を通じて「なぜ今就職したいのか」「この業界・職種を志望する理由は何か」を明確化し、面接で熱意を具体的に伝えることが必要です。
スキル不足や専門知識の欠如
新卒とも中途とも異なり、既卒者には「専門スキルが中途採用レベルに達していない」と判断される場合が多いです。
特にITや資格重視の業界では、未経験者への門は狭く、プログラミングや業界固有の知識がないと足切りされることも。
中途の場合、企業は採用後すぐに成果を出せる人材を求めるため、資格取得やスクール受講の実績を用意しておくと評価が変わりやすいです。



応募前に業界や職種に関連する具体的なスキルを磨いておくことで、企業の不安を和らげる効果も!
コミットメントや定着率への懸念
既卒者が「本当に長く働いてくれるのか?」という点は、採用担当者が気になるポイントです。
既卒期間中に仕事をせず、再就職を目指す背景には人それぞれ事情がありますが、企業側には「すぐに辞めてしまうのでは、、、」という不安が生じやすいのが現実です。
これを払拭するためには、長期的なキャリアビジョンを示し、「将来どのように社内で成長し貢献したいか?」を具体的に説明することが有効です。



アルバイト期間があるなら、そこで得た経験やスキルなどもアピールできます!
厳しい!?既卒者が就職する上での強み


厳しいと言われる既卒の方の就職。
しかし”既卒の方には新卒にはない強み”もあります。
それが次の4つです。
- 社会人経験を活かせる
- すぐに勤務ができる
- 自分に合った会社を探せる
- 資格を取るにも有利
社会人経験を活かせる
既卒の方の中には、アルバイトで生計を立てている方も多いです。
そのため、社会で働く最低限のマナーや行動には最低限対応できるはずです。



企業側も学生生活しか知らない新卒者より、安心して内定を出しやすくなります!
すぐに勤務ができる
卒業する日程が決まっている学生や現職中の転職者に比べ、既卒者は入社日に柔軟に対応できます。
会社によっては急募で人を募集しているところも少なくありません。
そうなってくると「いつでも働き始められる」既卒者の方が魅力的に映ります。
自分に合った会社を探せる
既卒の方の就職は自分に合う会社を探すことが可能です。
新卒の就職は「どこかに内定をもらわないと・・・」と焦り、自分の希望と違ったり・合わない会社で働くこともめずらしくありません。



既卒の場合、ある程度の時間をかけて会社選びができるため入社後のミスマッチは少なくなります!
資格を取るにも有利
アルバイトなどで働く既卒の方も、比較的スケジュール管理も柔軟に動けます。
そのため仮に実務経験がなくても、資格を取得後に応募することも可能です。



取得後に就職活動を行えば、既卒になっていた理由もしっかりと説明できます!
既卒者が就職する方法


既卒者が就職する方法としては次の4つがあります。
- 就活サービスを使う
- ハローワークを使う
- 企業のHPから応募する
- 求人広告から応募する
就活サービスを使う
既卒者の就職で1番代表的なものが、求人サイトや転職エージェントといったサービスを使うものです。
こういったサービスなら求人の検索はもちろん、履歴書や職務経歴書の作成、企業からのスカウトまで受けることが可能です。



転職エージェントであれば、プロから求人紹介・必要書類の添削・面接対策といった就活全体をサポートしてもらえます!
ハローワークを使う
ハローワークを使うのも既卒者の就活では有効な方法の一つです。
ハロワは公的機関が運営しているサービスです。
そのため企業側も無料で求人掲載できるため、求人数の多さは最大のメリットと言えます。



ハロワは無料がゆえにブラック企業が混じっている可能性もあるので、利用する場合には注意が必要!
企業のHPから応募する
応募したい会社がある方は、企業の公式サイトから求人応募する方法もあります。
この場合、自分の興味のある仕事であるため、入社後のミスマッチを少なくできます。
またサイト経由で応募することで、その企業への応募度の高さもアピールできるでしょう。
求人広告から応募する
書店で売っている求人誌や街で見かける求人募集といった、求人広告も立派な応募手段です。
こういった求人広告は地域に密着したものが多く、家の近くで働ける場所を探している人にはピッタリです。
その反面、アナログ的な探し方になってしまうので勤務地や職種が限られてしまうのはデメリットと言えるでしょう。
既卒者が就職活動をするオススメの時期


既卒者が就職活動するタイミングは大きく分けて【1〜4月】【10〜11月】の2つです。
このタイミングは一般的な求人が増える時期で、既卒であってもこの時期に活動をするのをオススメします。
ですので求人が増える1~2ヶ月前には動き出せるように準備しておきましょう。
既卒者が狙うべき職種・業界


既卒者向けの求人は、新卒採用や中途採用と比べて数は少なくなりますが、探し方やアプローチを工夫すれば十分にチャンスがあります。
ここでは、「未経験でも比較的入りやすい職種」「既卒者を歓迎しやすい業界」について解説していきます。
営業職(法人・個人問わず)
営業職は「コミュニケーション能力」「目標達成意欲」が重視されるため、既卒者でも挑戦しやすい分野です。
商品知識や営業手法は入社後に学べることが多く、ポテンシャル重視の採用を行う企業も少なくありません。
特に中小企業やベンチャー企業では、学歴や職歴よりも人柄を重視するケースが多く、既卒者の採用実績がある企業もあります。



営業経験を積むことで、後々はマネジメントやコンサルティングなど幅広いキャリアパスが開ける点も魅力!
IT・Web業界(未経験可ポジション)
IT・Web業界は人手不足のため、プログラミングスクール修了者や独学で学んだ既卒者でも採用されるチャンスがあります。
エンジニアリングやデザイナー、マーケティングなど、未経験者向けの研修制度を設置している企業も増加しています。
既卒期間中にオンライン講座やスクールでスキルを習得し、ポートフォリオを作成しておけば、未経験枠で十分戦えるでしょう。



IT業界でキャリアを積むと、将来的にはフリーランスやリモートワークなど多様な働き方も視野に!
事務・営業事務職
事務職や営業事務職は、専門的な資格やスキルがなくても応募しやすく、既卒者でも比較的門が広い職種です。
ExcelやWordといった基本的なOA操作ができれば、応募時点でのハードルが低くなります。
さらに、数字入力や資料作成などの経験を学生時代に積んでいれば、自己PRにも活かせるでしょう。
事務職で経験を積むことで、将来的には総務・人事・経理など、社内の管理部門へのキャリアアップも目指せます。
製造業・技術職(未経験者向け研修あり)
製造業の中には設備操作やライン作業からスタートし、後に技術者として育成する企業もあります。
未経験者向けに研修制度を整えている工場やメーカーを選ぶことで、既卒者でもスムーズに就職しやすい環境が整っています。
特に自動車部品や食品加工などの業界は人手不足が続いており、採用が積極的です。
将来的には品質管理や生産管理などの専門職にキャリアを広げる道もあるため、手に職をつけたい方に向いています。
サービス業(ホテル・小売・飲食など)
接客力やコミュニケーション能力を活かせるサービス業も、既卒者が狙いやすい職種と言えます。
ホテルや飲食チェーン、アパレル小売店など、人材確保が難しい業界では未経験者を積極的に採用し、教育体制を整えている企業が多くなっています。
特に立地の良い店舗やホテルでは研修制度が充実しており、基礎をしっかり学べる点が魅力。
将来的には店長やスーパーバイザー、本部職へのキャリアパスも見据えられることが多いため、長期的なキャリア設計にも役立ちます。
介護・福祉業界
高齢化が進む日本では介護・福祉分野の人材不足が深刻であり、「未経験者歓迎」の求人が豊富に存在します。
介護職員初任者研修など、資格取得支援制度を設けている施設も多く、働きながら収入を得つつ資格を取得できるメリットがあります。
社会貢献性が高く、安定した雇用を望む人にとっては将来性も見込める分野です。



「人と接することが好きな方」「誰かの役に立ちたいという思いが強い方」には、特に適しているでしょう!
既卒者におすすめの転職エージェント活用法


既卒で初めて就職活動をする場合、自己流だけではどうしても情報不足やノウハウ不足になりがちです。
そこで、転職エージェントを活用することで【求人紹介・書類添削・面接対策】などを無料でサポートしてもらい、就職成功率を高めることができます。
ここでは、既卒者が転職エージェントを賢く利用するためのポイントを解説します。
既卒歓迎の求人を多数保有しているエージェントを選ぶ
すべてのエージェントが既卒に強いわけではありません。
既卒者向けの求人を多く扱っているエージェントを選ぶことで、希望条件に合った企業を効率的に紹介してもらえます。
登録前に公式サイトで「既卒可」「第二新卒」「ポテンシャル採用」などのキーワードで検索し、どれだけ求人があるかを確認すると良いでしょう。
キャリアアドバイザーとの相性を重視する
転職エージェントではキャリアアドバイザーが担当につき、応募企業の紹介から面接アドバイスまで行ってくれます。
しかし、アドバイザーとの相性が合わないと、的外れな求人を紹介されたり、コミュニケーションがうまくいかないことも。
対面・オンライン面談で実際に話してみて、あなたの状況を理解してくれるかどうかを見極めましょう。



相性が悪ければ良い結果は出ないため、なるべく早めに判断するのがベスト!
自己PRや志望動機のブラッシュアップを依頼する
既卒者は経験値で劣る分、書類選考で「何を売りにすればいいか?」を悩むケースが多いです。
エージェントに自己PRや志望動機を添削してもらい、既卒ならではの強みを引き出してもらいましょう。
プロの視点で、経験の少なさをカバーできる書き方や面接での受け答えを教えてもらえるので、初めての就活でも安心して臨めます。



厳しい意見も大事ですが、落ち込むほどなら「他のサービスを使う」「担当を変えてもらう」なども必要!
既卒者が転職サイトや転職エージェントを利用する流れ


既卒者が転職サイト・転職エージェントを利用する流れは次のとおりです。
実際に転職サイトを利用する前に、まずは自己分析をしましょう。
転職したい理由や希望する仕事、年収、勤務地などをメモに箇条書きで出してみるとわかりやすくなります。
そして書き出したものの中で優先順位をつけていきます。
自己分析が終われば、次は求人サイトに登録していきます。
その際に自分のプロフィールや経歴、希望条件などをなるべく細かく入力しましょう。
後に企業からスカウトを受ける際にもこうした情報は細かい方がメリットが大きいです。
登録が終わったら、実際に就職したい会社を探していきましょう。
なるべく条件を絞って応募先を決めていきたいと思いますが、早めに就職先を見つけたい場合には2〜4社ほどは応募できるようにしましょう。
応募したい会社が見つかったら、求人サイトを通して応募していきます。
応募が完了すると相手の会社から連絡が届きます。
応募が終わると必要書類の提出になります(書類選考の状態によってはないことも)。
一般的には履歴書や職務経歴書があれば大丈夫ですが、デザイナーやエンジニアといった少し特殊な仕事になってくるとポートフォリオの提出がある場合もあります。
こうしたポートフォリオの制作は人によって時間がかかることもあるので、少しずつ作っておくのも良いかもしれません。
無事に書類選考を通過できると、いよいよ面接です。
履歴書や職務経歴書、ポートフォリオなど応募先から案内のあった必要書類を持って面接会場に向かいましょう。
面接回数としては通常なら2〜3回ほどです。
内定が決まれば、無事に就職活動が終了となります!
既卒でも就職することは十分に可能!
この記事では、既卒者の就職が難しいと言われる理由から強み、就活を成功させるポイントなどについて解説してきました。
「既卒者の就職は厳しい」と言われることはありますが、正社員として働いていくことはもちろん可能です。
ただ、既卒者には新卒や中途と異なる難しさがあり、準備をしっかり行い、自分の強みを明確にすること重要になっていきます。
特に「空白期間の説明」「志望動機の明確化」「転職エージェントの活用」は必須事項ととらえ、着実にステップを踏んでいきましょう!