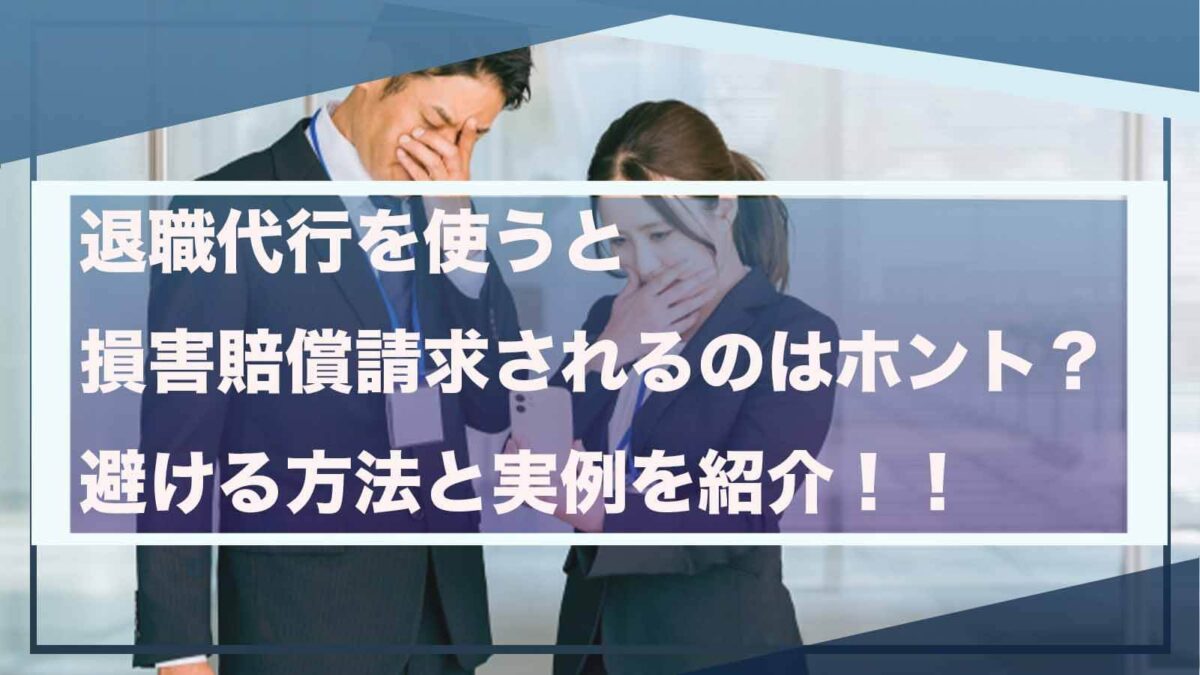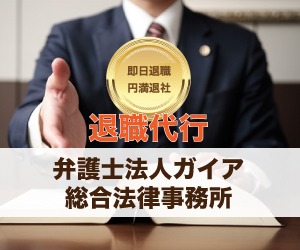- 退職代行の利用で損害賠償請求される可能性
- 損害賠償を避ける方法
- 退職時に損害賠償請求されるケース
「上司に直接伝えづらい」「退職を拒否された」など理由から退職代行サービスを利用する方は増えています。
情報を集めるためネットを検索していると、『退職代行を使うと損害賠償請求される』という噂を目にする方もいるでしょう。
せっかく会社を辞める手段を見つけたと思っても、これでは余計に不安を感じてしまいます。退職代行サービスを利用した場合の損害賠償のリスクについては、いくつかの点を理解しておく必要があります。
基本的には退職代行を利用したことで損害賠償に繋がることは少ないですが、状況によっては損害賠償の請求が行われる可能性もあります。
そこでこの記事では、退職代行を利用すると損害賠償請求される真偽から、避ける方法などについて詳しく解説していきます。
\安心安全の弁護士に依頼する!/
退職代行を利用すると損害賠償請求されるのはホント?

退職代行の利用を考える中で、「損害賠償のリスクが気になる」という声をよく耳にします。
特に法律や契約に不慣れな方にとっては、「退職代行で本当に安全に辞められるのか?」「企業から損害賠償を請求されることはないのか」?といった不安がつきまとうでしょう。
ただ、結論としては、退職代行を利用しただけで損害賠償請求されることはほぼありません!
損害賠償請求の背景と注意すべきポイント
退職代行における損害賠償請求のリスクは、主に労働契約や就業規則の理解不足からくるものです。
労働者には原則として”自由に退職する権利”があります。
ですが、会社側が「業務に著しい損害が出た」と主張する場合、損害賠償の対象とされる可能性はゼロではありません。
特に、契約書に記載された義務を履行していないとみなされるケースでは、トラブルが起きやすくなります。
また、業者との間に明確な合意や説明がないまま退職手続きを進めた場合、本人が知らぬうちにトラブルの原因になってしまうこともあります。
退職代行利用時におけるリスク管理の基本
退職代行を安心して利用するには、事前の準備が欠かせません。
まずは、業者が対応できる業務の範囲を確認することが第一歩です。
不明点がある場合はその場で質問し、納得できるまで説明を受けることが必要です。
リスクを最小限に抑えるためには、曖昧な点を残さず、すべてをクリアにしたうえで進める姿勢が求められます。
 SUSUMU
SUSUMU上司や会社から「今辞めたら損害賠償だ」と言われたとしても、それは単なる脅しと考えて大丈夫!
\27,500円から弁護士に依頼できる!/
退職代行を利用しても損害賠償を避ける4つの方法


退職代行サービスを利用する際は、契約内容や手続きの透明性が非常に重要です。
しかし、ごく一部の悪質な企業は”嫌がらせ”を目的として、実際に損害賠償請求を行ってくる可能性もあります。
ここでは、損害賠償リスクを最小限に抑えるための具体的な対策を整理していきます。
対策を徹底することで、安心してサービスを利用できる環境を整えることができるでしょう。
- 弁護士の退職代行へ依頼する
- 費用面で難しいなら労働組合へ依頼も
- 退職代行業者の実績と信頼性の確認する
- 可能な限り引き継ぎを行う
- 就業規則もなるべく守る
弁護士の退職代行へ依頼する
「退職の際に会社ともめた社員が居た」など、会社から損賠賠償される可能性がある場合は、弁護士が運営する退職代行を選ぶのがベストです。
民間や労働組合も参入している退職代行の中で、法律問題を解決できるのは弁護士だけです。
仮に弁護士以外のサービスに依頼し訴えられてしまったら、新たに弁護士を雇うことになってしまいます。



「辞めたら訴える」と言っていた会社側も、連絡をしてきたのが弁護士だとわかると大人しく引き下がる可能性も!
費用面で難しい場合は労働組合へ依頼も考える
弁護士へ退職代行を依頼する場合、約5〜10万円の費用がかかってしまいます。
そのため、「費用をどうしても抑えたい」方は労働組合の運営する代行サービスでも良いでしょう。
労働組合への依頼する費用は約3万円ほどと、民間と比べてもほとんど変わりません。
また、未払い賃金の請求や有給取得の交渉なども団体交渉権を使用することで対応してもらえます。
退職代行業者の実績と信頼性の確認する
業者を選ぶ際には、過去の実績や口コミ、SNSでの評判を丁寧にチェックしましょう。
実績豊富で信頼されている業者は、リスク管理やトラブル対応にも慣れており、安心して依頼できます。
「広告に出たから」や「料金が安いから」だけで判断せず、第三者の評価にも目を向けることが重要です。



ただ、業者自体が評価サイトやレビューを行う釣りもあるので注意が必要です!
可能な限り引き継ぎを行う
退職代行を利用する場合でも、企業との連絡が完全に絶たれるわけではありません。
必要に応じて、引き継ぎやコミュニケーションを代行業者と連携して行うことが重要です。
無理に会社に残るのはおすすめしませんが、ある程度計画を立てて退職できるようなら、引き継ぎ資料やファイルを作っておくと良いでしょう。
企業との誤解を防ぎ、スムーズな退職につなげるための配慮が、損害賠償リスクの低減につながります。



退職代行へ依頼する時点で資料作りが終わっていなくても、後から会社側に郵送で送れば問題ありません。
就業規則もなるべく守る
損害賠償請求されるリスクを少なくするためには、会社の社内規定や就業規則をできる限り守っておいた方が良いでしょう。
ただ、そうはいっても退職代行を利用すると「急な退職になることも多い」など、規則に対応するのが難しい部分もあります。
ですので、体や心に限界が来ている方は、ご自身のことを最優先にして行動すると良いかもしれません。
弁護士が運営するオススメの退職代行サービス
「辞めたら損害賠償請求だと脅された」
「会社とトラブルになるのは避けたい」
この場合に1番頼りになるのが弁護士による退職代行サービスです。
法律のプロである弁護士なら、会社から脅されている場合をはじめ、未払い賃金の請求や有給取得の交渉など幅広い業務に対応してもらえます。
弁護士法人みやび


| 弁護士法人みやび | |
|---|---|
| 運営元 | 弁護士法人 |
| 料金 | 55,000円(税込)+実費(郵送料など) |
| 即日対応可能 | 可 |
| 連絡手段 | LINE、メール |
弁護士法人みやびが運営する退職代行サービス。
退職代行大手の法律事務所のため経験豊富なので安心して依頼でき、スタッフ対応が丁寧なことも好評です。
当然、非弁行為の心配もないので、給与の未払いや残業代の請求などにもしっかりと対応してくれるのも良い点です(成功報酬として回収額の20%をオプション料金として支払う)。
\27,500円から弁護士に依頼できる!/
退職110番


| 退職110番 | |
|---|---|
| 運営元 | 弁護士法人 |
| 料金 | 43,800円(税込) |
| 即日対応可能 | 可 |
| 連絡手段 | メール、電話 |
弁護士法人あおばが運営する「退職110番」。
1番特徴は代表が弁護士資格だけでなく、社会保険労務士の資格を持った労働問題の専門家という部分です。
未払い給与の請求や損害賠償といった会社とのトラブルを抱えている方にも頼りになるサービスとなっています。
退職手続き書類の手配や離職票の請求なども代行してくれるので安心です。
退職する際に損害賠償請求される可能性のあるケース8選


退職代行サービスを利用したからといって、損害賠償請求されることはほぼありません。
ただし、企業が損害賠償に踏み切る事例も過去には存在します。
ここでは、あくまで一般的に想定されるリスクについて説明し、事前に知っておくべき注意点を整理します。
- 即日退職による業務への支障
- 無断欠勤・無断退職を行った
- 会社の機密情報を持ち出した
- 備品の破損や紛失を行った
- 損害を与えた
- ネットで会社や社長の名誉を傷つけた
- 引き抜きや勧誘を行った
- 退職通知の不備による不利益が発生した
即日退職による業務への支障
たとえ退職代行を使ったとしても、労働者としての契約義務を果たさなかった場合、企業から契約違反とみなされる恐れがあります。
たとえば、就業規則で定められた退職の申し出期間を無視して即日退職した場合などが該当します。
こうした手続きの不備が企業に損害を与えたと判断された場合、損害賠償の対象になる可能性があります。
また、プロジェクトの途中や繁忙期など、退職によって会社の業務が著しく妨げられた場合、会社側が「労働者の退職が会社に損害を与えた」と主張することがあります。



損害賠償請求を行う場合には「具体的な利害と因果関係の証明」が必要なので、現実にはなかなかハードです!
無断欠勤・無断退職(バックレ)を行った
無断欠勤を続けたり、無断退職(バックレ)を行うのはリスクが高く、損害賠償請求などの厳しい対応が取られることがあります。
特にバックレについては雇用契約書に定めている企業もあり、損害賠償にならなくても、減給や懲戒解雇されてしまうことも考えられます。
例えば公務員の方の場合、「10日以内の欠勤で減給や戒告、21日以上の欠勤で免職や停職」となっています
会社の機密情報を持ち出した
企業に勤める際、多くの場合で秘密保持契約を結んでいます。
そのため、退職時に「社外に情報を持ち出す」「意図せずに機密情報が漏洩した」などの場合は、損害賠償請求に発展するリスクがあります。
こうした情報が社外に持ち出されてしまうと、会社の信用を下げ、多大な損害を与えてしまう可能性も高いためです。
これは退職代行利用時の退職にかかわらず、常に注意が必要なポイントでもあります。



パソコンや資料などは辞める際にしっかりと返却しましょう!
備品の破損や紛失を行った
会社から借りているPCや社員証、社用車などは退職後に返却するのが基本です。
こうした物を紛失させたり、壊したりしたケースでも損害賠償請求されてしまいます。



仮に破損・紛失していた場合には、退職する前にしっかりと報告しておくのが大切です!
損害を与えた
業務の引継ぎが不十分・全くしない場合、後任者が業務を円滑に遂行できず、企業に実損が出る可能性があります。
特に、プロジェクトの進行やクライアント対応が遅延した場合など、目に見える損害が出た場合は要注意です。
- 取引先からクレームが入った
- 取引先との契約が解除になった
- 会社の業務自体が停止してしまった など
このような場合、企業が損害賠償を主張する根拠として扱われることもあります。
よほど特殊な職業に就かれている場合を除けば、しっかりとした引き継ぎはできなくても後任の方へ資料やファイルをまとめておくことで、会社も賠償請求はしないでしょう。
ネットで会社や社長の名誉を傷つけた
SNSなどのネット上で会社や社長の悪口を書き、それがもとで「会社の売り上げが落ちる」などの損害が生まれると損害賠償へつながる可能性もあります。
例え在職中の場合でも減給や停職にもなりかねませんので、会社や上司に不満が溜まっていたとしてもSNS上での悪口や中傷はやめましょう。



転職活動を行う際も応募先がSNSをチェックする場合もあるので注意が必要!
引き抜きや勧誘を行った
ご自身が退職する際、同僚の引き抜きや勧誘を行うと損害賠償請求されることがあります。
社内規定で引き抜きについて定めている会社はもちろん、同僚と同時退社したことで会社側の売り上げが減ることが予想できます。
損害賠償請求される危険性を下げるためにはこうした行動も控えましょう。
退職通知の不備による不利益が発生した
企業が求める退職通知の形式やタイミングに反する方法で通知がなされた場合、企業の業務運営に支障をきたす可能性があります。
たとえば、人員配置や顧客対応に大きな影響が出た場合、損害賠償の請求根拠とされることもあるかもしれません。
信頼できる退職代行サービスの選び方


代行業者選びは、損害賠償リスクの有無に直結するため非常に重要です。
信頼性の高いサービスを選ぶことで、不要なトラブルを回避し、安心して依頼することができます。
ここでは、信頼性を見極めるためのポイントや選定基準を具体的にご紹介します。
会社選びの基準は実績・評判・透明性
まず注目したいのは、代行業者の実績やこれまでの依頼件数です。
多くの実績がある業者は、それだけ多くのケースに対応してきた経験があります。
ネット上の口コミや評判を確認することで、利用者の満足度やトラブル発生率を把握できます。
さらに、「料金や契約内容がきちんと提示されているか?」どうかも信頼性の重要な指標になるでしょう。



利用時に賠償請求までいくケースはほぼないため、「請求されたケースがあるか?」だけで業者を選ぶのは難しいです!
契約書と説明の明確さを確認する
契約書には、損害賠償や免責事項についての記載があることが多いため、その内容をしっかり読み解くことが必要です。
不明点があればその場で質問し、納得できるまで説明を受けるようにしましょう。
特に事前面談や無料相談を設けている業者がほとんどなので、依頼前に不安を解消することが可能です。
サポート体制とトラブル対応の実績
トラブルが発生した際にどのようなサポートが受けられるかも、重要な判断材料です。
実際に対応してきたトラブル事例やその際の対応の迅速さ・丁寧さなどを確認しておくことで、万が一の際にも冷静に対処してくれるはずです。
利用者に寄り添ったサポート体制が整っている業者を選ぶことが、安心して利用するための鍵となります。



無料相談などでの対応からサポート体制を見極める方法も有効です!
退職代行利用時の損害賠償について:まとめ
この記事では、退職代行利用時の損害賠償請求の真偽から避ける方法、請求される可能性のあるケースなどについて詳しく解説してきました。
退職代行を利用したからといって、損害賠償請求されることはほぼありません。
ただし、退職の方法やタイミングによっては、業務に影響を与えた場合に損害賠償が請求されるリスクがあります。
また、勤務先によっては嫌がらせなどの理由から実際に訴られる可能性もあります。
会社から損害賠償請求のリスクは、正しい知識と事前の対策によって大きく減らすことが可能です。
契約内容の確認や信頼できる業者選びなど、一つ一つのステップを丁寧に行うことで、不安を払拭した状態でサービスを利用できるでしょう!