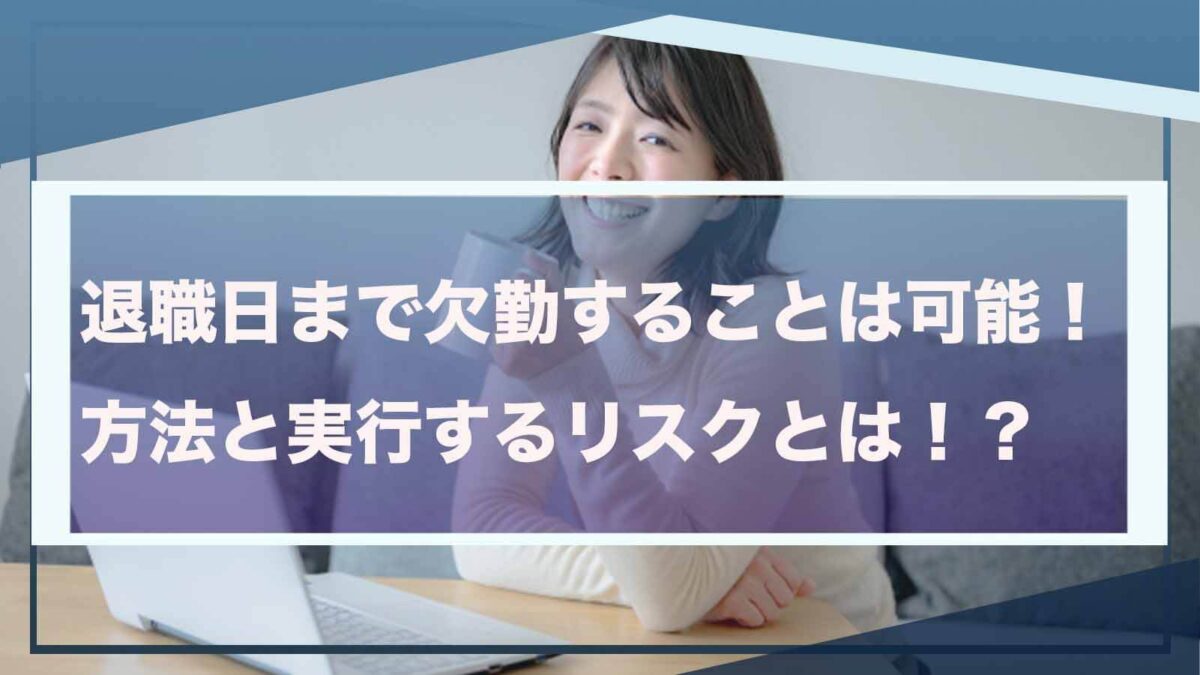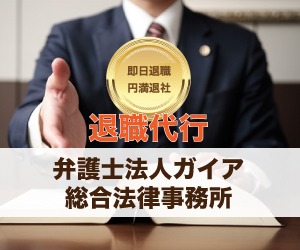- 退職日まで欠勤できる理由
- 退職日まで欠勤した場合のリスク
- 実際に退職日まで欠勤する方法
職場に対して不満や悩みがあり退職を考えている方なら「退職日まで欠勤して会社には出社したくない、、、」と思っている方もいるのではないでしょうか?
まず結論として、”退職日まで会社を欠勤する”ことは可能です。
ですが、実行する場合にはリスクもあるので注意も必要です。
そこでこの記事では、退職日まで会社を欠勤できるかの真偽から実行するリスク、欠勤する方法について解説していきます。
\退職成功率100%中!!/
退職日まで欠勤することは可能!

冒頭でもお話しした通り、”退職日まで欠勤する”ことはできます。
というのも正社員などの無期雇用の方について、民法627条では次のように書かれています。
つまり、正社員の方ならいつでも会社を辞めることが可能で『退職したいと伝えれば2週間後には辞められる』ということになります。
この2週間について「必ず出社しなければならい」といったことは書かれていないため、有給などを使えば出社の必要もありません。
これらの仕組みを正しく理解しておくことで、欠勤が続いた後でもスムーズに退職手続きを進められます。
まずは、法律と規則の観点から「なぜ欠勤したまま退職ができるのか?」を確認しておきましょう。
労働契約法に基づく退職の意思表示
労働契約法では、労働者が退職の意思を相手方に伝えさえすれば、「原則として2週間後には退職できる」と定められています。
このため、正社員なら欠勤中であっても退職の意思表示が有効です。
また、伝え方は口頭でも書面でも構いませんが、後々のトラブルを避けるため書面での提出が推奨されます。
会社が欠勤を理由に退職を拒むことは、法律上認められていません。
万が一、拒否された場合でも、労働基準監督署への相談や退職代行サービスの利用などで辞めることが可能です。
就業規則・就業規程上の取扱い
多くの会社では就業規則に「退職届受理」「退職日設定」の規定があり、欠勤日数によって退職日の延長が制限されることはありません。
例えば「退職日の1ヶ月前までに退職届を提出する」などの規程に従えば、欠勤期間を理由に退職日を先延ばしされることは基本的にないのです。
そもそも会社の規則より、法律の方が優先させるため退職の意思を伝えれば2週間後に辞められます。
規則の内容を把握しておけば、会社側からの不当な交渉に対しても毅然と対応できます。
 SUSUMU
SUSUMU疑問点があれば、専門家や退職代行の無料相談などを活用しましょう!
社会保険・雇用保険への影響
欠勤中でも社会保険や雇用保険の資格喪失日は、最終出勤日の翌日ではなく、会社が手続きを行った日付となります。
このタイミング次第で失業給付の申請開始時期や給付額が変動するため、事前の確認が必須です。
欠勤したまま退職する場合は、保険資格喪失証明書や離職票の発行日を把握しておくことも大切です。
また、退職後すぐに再就職先が決まっていない方は、ハローワークでの手続きが遅れないように段取りをしておきましょう。
会社側の対応パターン
欠勤が続くと会社はまず安否確認の連絡を入れ、その後、就業規則に基づいた警告や退職勧奨を行ってくるケースがあります。
しかし、正式な退職届が提出されれば、会社はそれを受理する義務が生じます。
退職拒否や退職日の先延ばしは法律違反となるため、強行されることはほぼないでしょう。
それでも不安な方は、退職代行を通じて会社に正式に意思表示をすることで、手続きが滞るリスクをゼロにできます。



もちろん無断欠勤やバックレなどを行うのは倫理的に良くありませんし、ご自身にとってもかなりのリスクがある!
欠勤したまま退職するメリット


欠勤したまま退職を進めることには、心身の健康を守りつつ手続きを進められるメリットがあります。
出社せずに手続きができるため、ストレスフルな職場環境から距離を置きながら退職・転職準備に集中できます。
ここでは欠勤したまま退職するメリットを4つご紹介していきます。
- 精神的ストレスの軽減できる
- 人間関係の摩擦も回避
- 退職準備に集中できる
- 面談・引き継ぎの負担軽減できる
精神的ストレスの軽減
仕事のプレッシャーや人間関係の摩擦から物理的に離れることで、心身への負担を大幅に軽減できます。
毎朝出勤する緊張感がなくなるため、精神的にリラックスした状態で退職準備が進められるでしょう。
また、自宅やカフェなどで書類作成や転職活動に集中できるため、効率的に動けるというメリットもあります。
ただし、完全に会社から切り離されてしまうと手続きの進捗状況が見えにくくなることもあるため、定期的に状況確認の連絡は必要です。



こうした点を押さえながら、自分のペースで手続きを進められるのが大きな強みです!
人間関係の摩擦も回避
「上司と反りが合わない」「会社でハラスメントを受けている」などの場合。
上司や同僚と直接顔を合わせずに退職手続きを行えるため、ネガティブな会話や引き留めに遭うリスクを抑えられます。
特に「退職理由を深掘りされる」「感情的なやり取りになる」といったケースを回避できるのもメリットでしょう。
退職代行を利用するなら、連絡は書面や代行業者を介して行うことで、不要な対立を避けたまま辞められます。
退職準備に集中できる
欠勤期間中は出社の義務がないため、退職に必要な書類作成や転職活動などにまとまった時間を確保できます。
これにより、慌ただしい中で不備のある書類を提出してしまうリスクも軽減できます。
通常の煩わしい退職手続きのほとんどを短縮できるため、次のキャリアへの移行もスムーズになります。
面談・引き継ぎの負担軽減できる
通常、退職前には上司との面談や後任者への引き継ぎ業務が発生しますが、欠勤を利用するとこれらを最小限に抑えられます。
また、退職代行を利用すれば、会社との連絡や書類の受け渡しのみで退職手続きが完了するケースもあります。
引き継ぎや各所への挨拶といった、精神的に負担の大きい業務を乗り越える必要がなくなります。
ただ、引き継ぎや挨拶なしでの退職は、上司をはじめ、同僚や取引先からの印象が悪くなることは間違いありません。
退職代行を使う場合でも、引き継ぎ資料やファイルなどを作成し、必要に応じて引き継ぎ業務にも参加するのがおすすめです。



退職代行を利用する時点で「会社の人間関係はどうでも良い!」と感じている方も多いかもしれません!
退職日まで欠勤した場合のデメリット・リスク


会社を辞める権利を使うのは労働者の自由です。
とはいえ、欠勤を続けながら退職する手法には、金銭的・手続き面などでのデメリットも存在します。
これらをあらかじめ把握しないと、想定外の損失やトラブルにつながる恐れがあります。
- 有給休暇の消化機会が喪失する可能性
- 会社からの連絡が続く
- 身元保証人に連絡がいく
- 退職金・手当の減額リスク
- 懲戒解雇される恐れがある
- 手続き書類の遅延トラブル
- 損害賠償請求される可能性もある
有給休暇の消化機会が喪失する可能性
欠勤扱いのまま退職すると、残存している有給休暇を消化できないケースが多くあります。
会社によっては「欠勤」と「有給」は別扱いで、欠勤日は有給と相殺されないためです。
その結果、有給消化分の給与が支払われず、損失になる可能性があります。
対策としては、事前に「欠勤ではなく有給申請」を検討するか、退職代行に有給交渉を依頼することを選ぶとよいでしょう。
会社からの連絡が続く
退職伝えた後、そこから出社も欠勤連絡もしなければ、当然会社からの連絡が何回も来ることになります。
「体調不良で倒れているのではないか?」
「事件に巻き込まれたのではないか?」
といったことを考えれば会社としては当然の反応です。



連絡に対応しないと上司や同僚が自宅を訪ねてくる可能性もゼロではありません。
身元保証人(両親)に連絡がいく
労働者との連絡がつかない場合には、緊急連絡先や身元保証人へ電話がいきます。
身元保証人は両親であることも多いので、会社に「退職したい」と伝えていたとしてもバックレなどを行うと家族や周囲の人にも影響を及ぼしてしまいます。
退職金・手当の減額リスク
欠勤日数が多いまま退職すれば、勤続年数や出勤率を基準に計算される退職金・各種手当の額が減少する可能性があります。
就業規則で「退職金は出勤率〇%以上が支給条件」といった規定がある会社も少なくありません。
また、ボーナスや精勤手当などの支給基準を満たせないことも考えられます。
就業規則を事前に確認し、「欠勤を有給扱いにできないか会社に相談する」「退職代行で条件交渉を依頼する」のが有効です。



退職代行を依頼する場合、交渉が行える弁護士か労働組合が運営する業者に依頼しましょう!
職種によっては懲戒解雇される恐れがある
会社や職種によって無断欠勤・バックレを行うと、『重いと懲戒解雇』『軽くても減給処分になる』こともあります。
特に公務員の方は民間企業の方とは違い、しっかりとしたルールが決められています。
先ほどの「退職を伝えれば2週間後に辞められる」という民法が使えない場合も多いので注意が必要です。
手続き書類の遅延トラブル
欠勤中は会社と直接コンタクトを取らないため、離職票や源泉徴収票などの必要書類が手元に届くまでに時間がかかる場合があります。
会社の総務なども欠勤者への対応に後回しをすることが多く、書類遅延が発生しやすいのです。
遅延が続くと、失業給付申請や確定申告などに支障が出る恐れがあります。
退職代行を依頼するなら書類手配を依頼するか、自分から会社側にリマインド連絡を入れる方法があります。
損害賠償請求される可能性もある
欠勤が続くと会社によっては損害賠償請求をされる恐れもあります。
会社に労働者を守る義務があるように、労働者にも労働を提供する義務があります。
ですので、会社に損害を与えると債務不履行として損害を請求されるかもしれません。



もちろん労働者側にしっかりとした理由があれば、こうした請求は認められないのでご安心ください!
退職日まで欠勤できる4つの方法


「会社に無断ではなく、退職日まで欠勤する方法はないの?」と感じている方にオススメの方法もあります。
それが次の4つです。
- 有給休暇を使う
- 体調不良として休む
- 医師の診断書を提出する
- 退職代行サービスを利用する
有給休暇を使う
退職を伝えてからの2週間、有給休暇を使って休む方法もあります。
ただしこの場合は、引き継ぎや会社への挨拶を全くしないことになるので、実行するのはかなり難易度が高くなります。
体調不良として休む
一番代表的なのが「体調不良が原因」と連絡し欠勤する方法です。
体調不良なら職場から怪しまれる可能性も低く、数日なら欠勤できるでしょう。



3日以上など欠勤が続く場合には、『病院へ行ったことの証明や診断書の提出が求められる』点には注意が必要!
医師の診断書を提出する
実際に体調が悪い場合には、医師に診てもらいその診断書を会社に提出する方が良いでしょう。
職場でのいじめやパワハラからうつ病などを発症するケースはめずらしくありません。
もし辞める原因がこういった問題だと、退職後に受け取る失業給付金の額の変化や会社側に損害賠償請求するかどうかにも影響を及ぼします。



いじめやパワハラに悩んでいる方は、自力で解決しようとせず、弁護士や退職代行などに相談することも考えておくと良いかもしれません!
退職代行サービスを利用する
「これ以上は会社に出社できない」と感じている方は、最初から退職代行サービスに依頼するのもおすすめです。
退職代行なら一度依頼してしまえばご自身から勤務先に連絡することなく、”即日退職”することも可能です。
有給を使い退職日まで出勤しない方法も、代行業者になら任せられます。
注意点としては、会社からの引き止めが予想できる場合には弁護士か労働組合の退職代行を利用しましょう。



労働組合なら未払い賃金の請求や有給取得の交渉なども可能で、弁護士なら損害賠償請求にも対応してもらえます!
\退職成功率100%中!!/
欠勤したまま退職する際の注意点


欠勤したままで退職手続きを進める場合、見落としがちなポイントを事前に押さえておかないとトラブルにつながるリスクもあります。
特に初めて退職代行サービスを利用する方は、次の注意点をチェックリストとして活用してください。
退職届の形式と提出方法
退職届は口頭やメールだけでは証拠として不十分です。
必ず文書で作成し、【氏名・退職希望日・提出日】を明記した上で、押印または署名を行いましょう。
郵送する際は書留や内容証明を利用して送付履歴を残すと、受理状況を証明できます。
提出後は、会社からの受理確認をメールや書面で必ず取得してください。



証拠が揃っていれば、万が一のトラブル時にも自分の立場を守りやすくなります!
会社との連絡窓口の明確化
退職代行を利用する場合、業者を通じて会社からの連絡がくることになります。
人事担当者や総務担当者の氏名・連絡先を事前に把握し、代行業者にも共有しておきましょう。
また、可能であれば自分の連絡先(メール・電話番号)を会社に届けておくのもありです。
これにより、書類の不達や伝達ミスのリスクを低減できます。
書類・証拠の保存と管理
退職に関わるやり取りはすべて記録として残しておくことが重要です。
メールのやり取りや郵送時の受領証、退職届のコピーなどを一元管理しましょう。
データ化してクラウドに保存しておくと、紛失リスクを抑えられて便利です。
退職後に必要となる書類(離職票、源泉徴収票、健康保険喪失証明書など)がスムーズに手に入らないトラブルを防ぐためにも、発行状況をこまめにチェックしてください。
精算スケジュールの事前把握
給与や有給、退職金の精算は会社ごとに締め日や入金日が異なります。
事前に退職日を基準にした精算スケジュールを確認し、「いつ何が振り込まれるのか?」を把握しておきましょう。
問い合わせ先もリストアップし、万が一の遅延時に速やかに連絡できる体制を整えておくと安心です。



退職代行を利用する場合は、これらの詳細を業者に共有しておくと良いでしょう!
退職代行サービスの利用範囲確認
代行業者によって、対応範囲や料金体系は大きく異なります。
会社への代行連絡だけでなく、有給交渉や退職金請求など、「どこまでカバーしているかどうか?」を必ずチェックしましょう。
追加料金が発生するケースやサポート期限も業者ごとに異なるため、契約前に見積もりとサービス内容を詳細に確認してください。



無料相談時に不安点をすべて解消し、自分に合った業者・プランを選ぶことがトラブル回避の鍵です!
欠勤したまま退職する具体的なステップ


実際に欠勤したまま退職を完了させるためには、段階的に手続きを進めることが重要です。
次の5つのステップを順番に行うことで、未経験者でもスムーズに退職が完了します。
ステップ1:欠勤開始と意図の明確化
まずは欠勤を始める際に、自分自身の退職意図を明確にしましょう。
一身上の都合として欠勤する場合は「退職を視野に入れている」旨を心の中で整理し、必要に応じて上司に連絡します。
欠勤理由は詳細に述べる必要はなく、「体調不良」や「一身上の都合」で十分です。
この段階で心の準備を整え、次に何をすべきかのスケジュール感を掴んでおくと、後の手続きがスムーズになります。



いきなり”一身上の都合で欠勤”といっても、絶対に細かい内容を聞かれることになります!
ステップ2:口頭での退職意思表示
欠勤開始後、上司または人事担当者に退職の意思を口頭で伝えます。
電話やオンラインミーティングでも構いませんが、会話内容を後で確認できるよう、要点をメールでまとめて送信しておくと安心です。



口頭で上司や会社側に伝えるのはハードルも高いため、基本は退職代行がおすすめです!
ステップ3:書面での退職届提出
本当に体調不良の場合など、きちんと上司・会社側が納得できる理由があるなら、退職届の提出や持参を行います。
氏名や退職希望日、提出日を記載し、押印または署名を忘れずに行いましょう。
郵送する場合は書留や内容証明を使い、送付記録を保管します。
会社からの受理確認(メールや印字入りの受領書)を必ず取得し、書面のコピーも自分で保管するのがベストです。
ステップ4:退職代行サービスの利用手続き
自力での退職に不安がある場合は、退職代行サービスを正式に依頼します。
まずは無料相談で自分のケースを確認し、見積もりとサービス内容に納得したら契約を締結しましょう。
契約後は代行業者が会社との連絡を一手に引き受けてくれます。



退職届の作成などは民間・労働組合では行えない点には注意が必要です(弁護士なら可能)!
ステップ5:最終書類の受け取りと精算確認
会社または業者から離職票、源泉徴収票、健康保険喪失証明書などの最終書類を受け取ります。
同時に、給与や有給・退職金の精算額と入金タイミングを改めて確認し、指定口座に振り込まれるかチェックしましょう。
万が一、不足や遅延があれば、担当者や代行業者に速やかに連絡してください。
退職代行サービスとは?未経験でも安心の選び方ガイド


「退職代行」の仕組みや業者の選び方を理解しておくことで、欠勤中の退職手続きをプロに任せた際にも後悔がなくなるはずです。
ここでは、サービス内容と比較ポイント、未経験者が安心できる業者の特徴を解説します。
退職代行サービスの主な業務内容
退職代行サービスは、労働者に代わって会社との連絡を一手に引き受けてくれる専門の業者です。
自分で会社とやり取りせずに退職できるのが最大のメリットです。
欠勤中で連絡が取りづらい状況でも、代行業者が確実に手続きを進めてくれます。
さらに、業者によっては未払い給料の請求や有休消化の交渉、転職サポートなどにも対応してくれます。
料金・サポート体制の比較ポイント
業者選びでは、基本料金に何が含まれているかを必ず確認しましょう。
未払い給料や退職金請求などは、別途料金が必要になることがあるため要注意です。
サポート体制としては、メールや電話の対応時間、返信速度などを比較ポイントにします。



安心して任せられる業者は、無料相談の段階でしっかりと不安を解消してくれます!
欠勤したままの退職について:まとめ
この記事では、退職日まで会社を欠勤できる真偽から実行するメリット・リスク、欠勤する方法などについて解説してきました。
欠勤したまま退職することは、制度上可能です。
しかし、体調不良などの特別な理由なく実行してしまうと両親に迷惑がかかったり、損賠賠償請求や懲戒解雇になる可能性もあります。
また、自分一人で実行することも難しいので、弁護士か退職代行といった第三者から会社に連絡してもらう方法がおすすめです。
安心感を持って次のステップへ進み、新しいキャリアをスタートさせましょう!